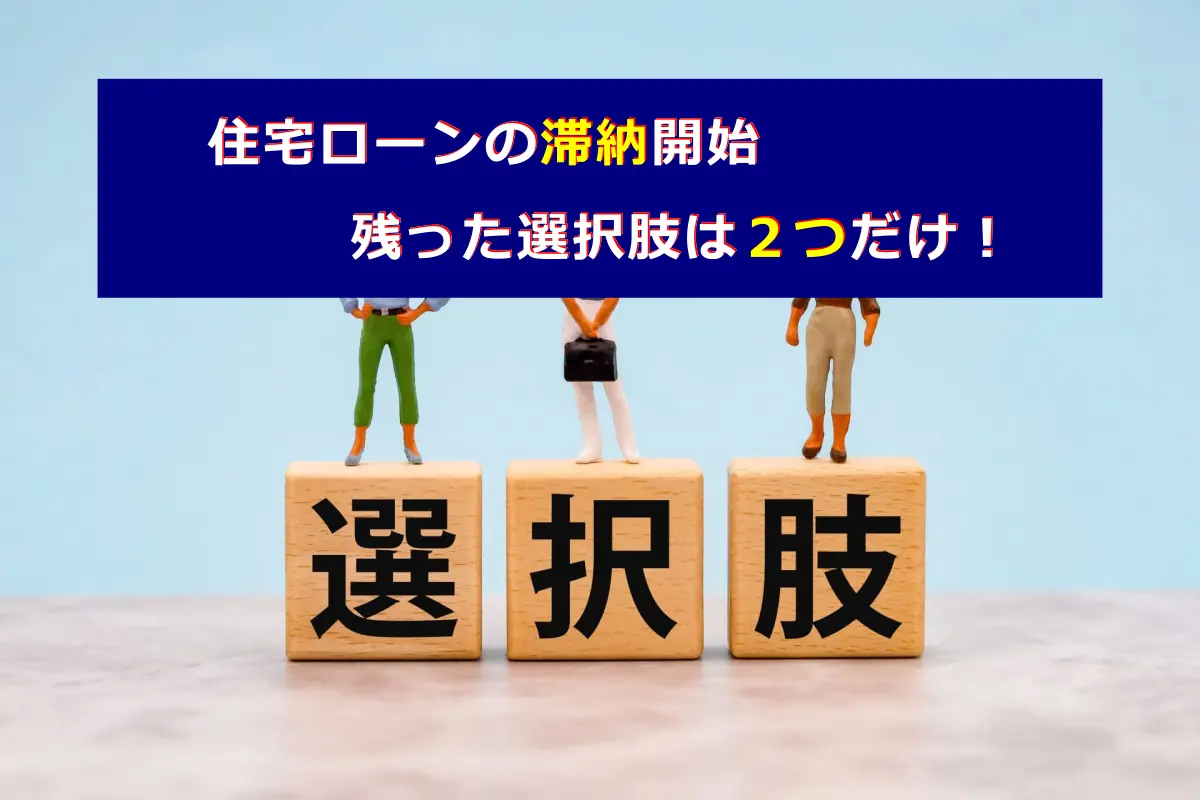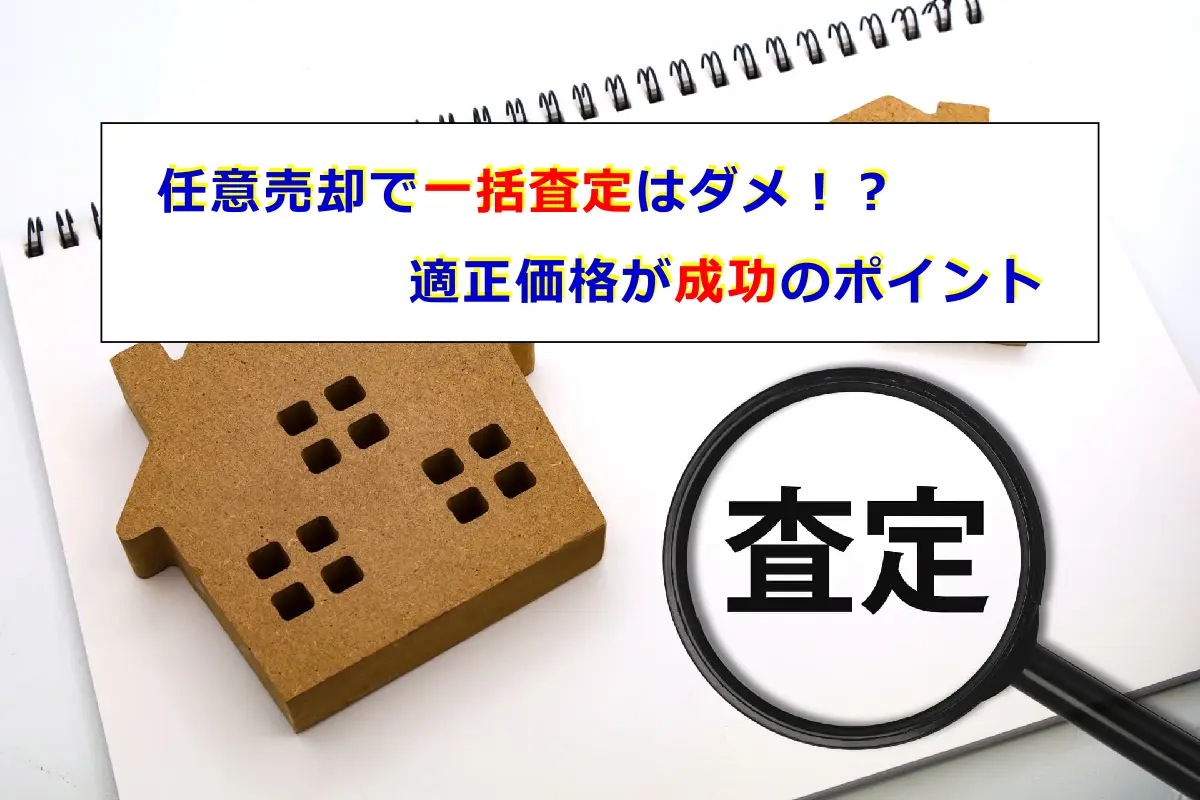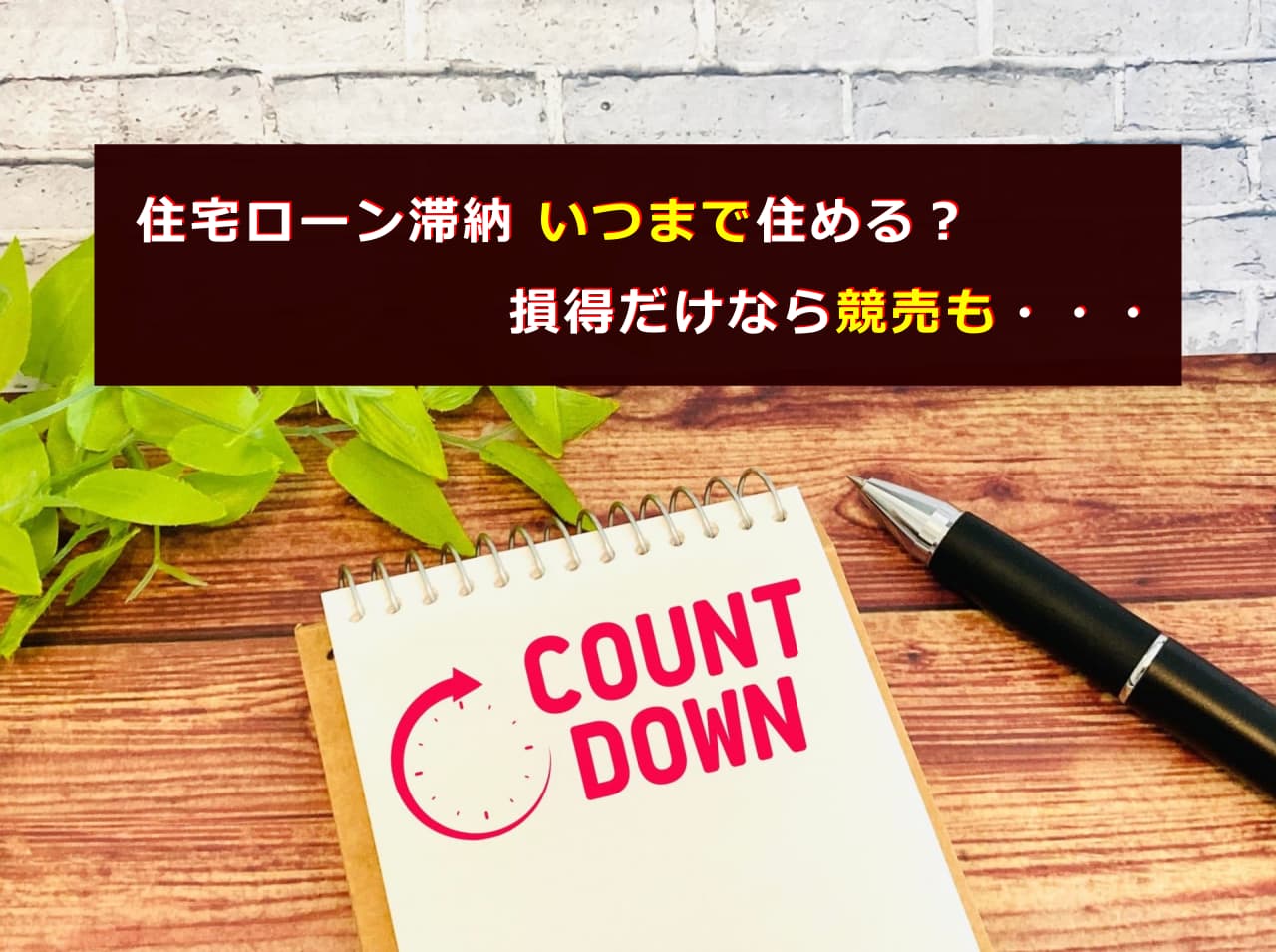土日祝日も受付中
任意売却の費用と売却後に税金はかかるの? 要注意ポイントをFPが解説

任意売却を検討する際に、その費用について大変気になることでしょう。
当然ながら、任意売却を含め「不動産を売却するには相応の費用」が必要です。
ただし、任意売却の費用については、お客様ご自身が用意する金額は極めて少なく、その点は安心できます。
住宅ローンや他の不動産担保ローンも同様に、返済が苦しくなると様々な費用を工面するのは大変なことです。
そのため任意売却は、費用負担を最小限に抑えながら不動産を売却し、借入金を返済することが可能になります。
また、任意売却は無事に済んでも「不動産を売却した際の税金はかかるのか?」
こちらについても、任意売却を検討せざる負えない状況では、非常に気掛かりな問題です。
任意売却の現場に携わるFP&不動産コンサルの有資格者が「任意売却の費用と任意売却後に課税されるケースについて」解説します。
目次
任意売却時に用意する金額が少ない理由

不動産を売買するとき、様々な諸費用が必要になります。
任意売却も通常の不動産売却も、売却に掛かる費用は、ほぼ同じと考えて差し支えありません。
しかし、通常の不動産売却との違いは、高額な諸費用のほとんどを「売却代金の中から支払うことを金融機関が認めてくれる」ことです。
任意売却で享受できる、非常に大きなメリットです。
つまり、任意売却の場合は「高額な諸費用を用意することなく不動産の売買」が可能となります。
任意売却の諸費用は売買価格に織り込み済!
任意売却にかかる費用一覧
2,000万円でマンションを任意売却した際の諸費用を以下の表にしました。
| 名 目 | 支 払 先 | 金 額 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 物件価格×3.3%+6.6万円 | 不動産業者 | 726,000円 |
| 抵当権の抹消費用等 | 司法書士 | 50,000円 |
| 税金や国民健康保険の滞納等による差押解除 | 役所 | 100,000円 |
| 管理費、修繕積立金の滞納分 | マンション管理会社 | 200,000円 |
| 引越し代 | お客様が受領します | 200,000円 |
| 諸 費 用 合 計 | 1,276,000円 | |
任意売却は上記のような、高額な諸費用を「売却代金の中から支払うことを金融機関が認めてくれる」と漠然と伝えられても、イメージするのも難しいものです。
そこで、上記の諸費用を更に図にしましたのでご覧ください。

諸費用の合計として「1,276,000円」必要となりますが任意売却の場合、お客様ご自身で用意する必要はありません。
「仮に住宅ローンの残債が3,000万円でも4,000万円以上であっても」お客様が用意する現金は印紙代の10,000円のみとなります。
※ (契約書に貼る印紙代はお客様の自己負担、上記の場合10,000円ですが、お客様が保管する契約書がコピーで構わなければ、印紙代が不要な場合もあります。)
尚、任意売却で売却代金から諸費用を支払う場合、「売買金額を上回るローン残高」が要件です。
任意売却なら金融機関は赤字でもOK
諸費用の詳細を順番に見ていきましょう。
仲介手数料
仲介手数料は、任意売却の取引を仲介した不動産業者に対して支払う費用です。
任意売却時の諸費用の中でも、大きなウェイトを占めます。
仲介手数料は、法律で上限が定められており、不動産の売買価格によって異なります。
〈仲介手数料の上限〉
- 800万円未満…30万円(税別)
- 800万円以上…売買価格の3%+6万円(税別)
なお、仲介手数料は取引が成立した場合のみ支払うものです。
仲介手数料の計算
仲介手数料の計算方法は簡単です。
前項に記載した「売買価格の3%+6万円」に消費税を足した金額が受領できる限度額となります。
また、売買価格が800万円を下回る場合、30万円に消費税3万円を足した金額が上限です。
新築マンションを購入者された方は仲介手数料と聞いても、あまりピンと来ないかもしれませんが、不動産の取引には賃貸・売買を問わず、不動産業者が仲介をするのがほとんどです。

売買金額が2,000万円の不動産の場合、図中の726,000円が仲介手数料となります。
任意売却の仲介手数料について更に詳しく
任意売却時の仲介手数料は、どのような流れで発生するのでしょうか?
まず、任意売却は不動産の売買取引のため、必ず「宅地建物取引業の免許」を有する者が関わります。
「宅地建物取引業の免許」を簡単に言いますと、不動産業を営むことができる免許です。
つまり、任意売却の取引とは不動産業者が、「売主と買主の間を取り持つ仲介」での不動産取引となります。
要するに、売手と買手をマッチングし取引を終えた場合のみ仲介手数料が発生する仕組みです。
任意売却が成立しない限り、仲介手数料は発生しません。
また、任意売却をスタートさせるための着手金などもありません。
仲介手数料は完全な成功報酬
抵当権抹消費用等
住宅ローンなど抵当権が設定されている不動産を売却するには、必ず抵当権を抹消する手続きが必要です。
抵当権抹消登記は不動産1個につき1,000円※かかりますが、マンションだと土地と建物でそれぞれ1,000円ずつかかることもあります。
このほか、不動産登記の内容を確認するための事前調査費用(1筆につき335円)や、手続き完了後に登記簿謄本を取得するための費用(1筆につき600円)もかかります。
この手続きは司法書士が担当するため、その報酬として1万円~2万円程度必要になります。
その他、任意売却の売主が引越しを済ませ、住所が変わっていると変更登記も必要となり更に1万円程度がプラスされます。
任意売却(通常の不動産売買も同様)では、上記費用をすべて含めて「抹消費用」と呼んでいます。
抹消費用は5万円程度で足りる
税金や国民健康保険の滞納等による差押解除

任意売却を検討するにあたり、解消しなければならないのは、税金や国民健康保険料(税)の滞納問題も実は深刻です。
多くのケースで、固定資産税を滞納されている方がほとんどです。
また、固定資産税に限らず税金の滞納は、任意売却の大きな障害となります。
滞納によって不動産が差押さえられた場合、任意売却するには「差押えの解除」は絶対です。
原則として、差押えを解除するには滞納している税金を全額納付しなければなりません。
そうはいっても、任意売却が必要な状況での全額納付は難しいでしょう。
こちらについても、売却代金の中から役所に滞納している税金などの納付を金融機関が認めてくれます。
しかしながら、限度もある!
数十万円単位の滞納金額ともなれば、さすがに金融機関も回収金額を削ってまで、任意売却を認めることはできません。
そうなると、「任意売却をあきらめるか?」
「税金の滞納分をご自身で工面する」以外、方法はありません。
滞納額が増えるほど任意売却のハードルも、より一層高くなってしまいます。
税金の滞納は極力避ける
あわせて読みたい

役所の差押えが障害に!税金や健康保険料の未納で競売も
景気の回復を実感している人が、実際は少ないような報道を見かけます。 その反面で財務省の発表によると令和4年度の一般会計の税収が過去最高となりました。 税収に関...
管理費、修繕積立金の滞納分
マンションの場合、修繕積⽴⾦や管理費の滞納分についても、金融機関は任意売却に伴う費用として認めてくれます。
仮にマンションの修繕積⽴⾦や管理費の滞納が無かった場合、任意売却に手慣れた業者であれば、むしろ修繕積⽴⾦や管理費については支払いをストップすることを提案します。
その理由としては、その分を新生活の準備資金に充て、転居を容易にするためです。
ただし、修繕積⽴⾦や管理費の滞納分については、マンションの管理組合が遅延損害金を請求します。
この遅延損害金を含め駐車場、駐輪場、専用庭、ルーフバルコニー等の利用料滞納分に関しては、お客様がご用意するケースがほとんどなので注意が必要です。
管理費や修繕積立金も工面の必要なし!
引越し代
任意売却の相談者の中には、日々の生活に困窮されている方も多く、実際に任意売却中、部屋の片付けをお願いしても、ゴミ袋を購入するお金が無い方もいらっしゃいました。
このままでは買手が付いても、お金が無くて引越せない状況に陥ります。
それでも、任意売却での取引を終えるには、空家にしなければなりません。
この様なケースでは、金融機関に対して、いくらか手元に現金を残してもらえるよう交渉します。
任意売却業者の交渉の末、引越し代の捻出が可能となっても、事前に用意してもらえる訳ではありません。
したがって、引越しに係る費用は事前に準備しなければなりません。
この点は、任意売却を希望される方は肝に銘じてください。
引越し時に引越し代や転居費用に利用できない訳
引越し代は、任意売却の取引終了時に金融機関が売却代金の中から認めてもら費用であるため、事前に用意してもらい、引越し先の入居費用等に充てることは不可能です。
また、ご理解いただきたいのは、金融機関は 「引越し代を必ず認めくれる訳ではない!」ことです。
最初から引越し代を見込んでの、任意売却はあまりお勧めできませんので、まずは無いものとの認識で準備してください。
その他、任意売却時の引越し代を認めてもらうと、「不動産売却に伴い課税されるケース」もあるため注意が必要です。
こちらについては後述します。
引越し代は認めてもらえないのが主流
任意売却の報酬は?
ここまで見てきた諸費用の中には、任意売却業者に支払う「任意売却の報酬」についての記載がありません。
実のところ、任意売却の報酬としての記載はありませんが、しっかりと計上されています。
名目としては、「 仲介手数料(物件価格×3.3%+6.6万円)」と表記され、任意売却業者に支払う報酬は、不動産売買に伴う仲介手数料となります。
報酬は仲介手数料として支払う!
仲介手数料は任意売却の必要経費
繰り返しになりますが任意売却では、この金額(仲介手数料)を金融機関は必要経費として認めてくれます。
依頼者が工面する必要がなく、安心して取引することができます。
もっとも仲介手数料については、任意売却の依頼時に書面化して交付しています。
報酬についての書面とは?
報酬に関することは、依頼する際にお客様と任意売却業者との間で媒介契約(売却の依頼書で3種類ある)を結び、その書面の中にも報酬の金額及び支払い時期も、きちんと明記されています。
現在、任意売却が進行中の方は確認してみてはいかがでしょう。
任意売却の報酬として認めるのは仲介手数料だけ

なぜ、金融機関は自らの回収額を減らしてまで、仲介手数料を売買代金の中から必要経費として認めるのか?
任意売却が金融機関にとっても、非常にメリットがあるからです。
そのため、お客様が様々な理由で任意売却が有効と考えたとき、その任意売却を依頼するのは宅地建物取引業の免許を与えられた不動産業者のみが対象となります。
また、金融機関が売却代金の中から任意売却の報酬として、支払いを認めるのは仲介手数料しかありません。
任意売却は不動産業者のみができること!
あわせて読みたい

住宅ローン滞納で残った選択肢は2つ!|なぜ任意売却に金融機関は協力するの?
住宅ローンや他の不動産担保ローンの返済が困難になったとき、インターネットで調べると「任意売却が有効な手段」となる説明を目にします。 それでも、任意売却はロー...
任意売却の相談に免許は不要なので注意も!
任意売却の相談窓口でも、任意売却ができるかは別問題です。
不思議なことに、任意売却ができない任意売却の相談窓口も、ネット上には多数存在します。
金融機関が任意売却の報酬として、唯一認めるのは不動産売買の仲介手数料だけとなり、任意売却の相談料等を報酬として認める金融機関はありません。
つまり、任意売却の報酬を受取る資格の無い者は任意売却ができない者となり、見極めるには細心の注意が必要です。
任意売却の相談及び依頼を迷っているなら、任意売却に精通する業者がお勧めとなります。
任意売却の相談料を金融機関は必要経費として認めない!
あわせて読みたい

任意売却の相談で気を付けるポイント「不安をあおる業者」はアウト!
任意売却を検討する際や依頼するにあたって、最初にすることは「相談先の業者選び」です。 任意売却の相談先は規制も無いため、インターネットで検索すると実に多くの...
任意売却の報酬を含めた諸費用の支払い時期
任意売却の費用の支払い時期は、不動産の売買契約を済ませ、買主に名義を変える日(決済日と呼びます)に同時に支払います。
この決済日に、買主から売主へ売買代金が支払われます。
売主は売買代金から、任意売却時の必要な費用を支払い、残りを金融機関に返済します。
要するに、任意売却の報酬である仲介手数料の支払い時期は「決済日」となります。
報酬の支払い時期は売買代金受領日
任意売却の費用負担が最小限で済むのは競売開始決定前
個々の経済状況が厳しい中で取組むのが任意売却です。
誰しも金銭的な余裕は、ほぼ皆無です。
その中で、いかに不動産を高値で売却し、借金を多く返済してもらうためには、金融機関も協力しなければ成果は望めません。
その結果、お客様が任意売却を望むならば、費用負担が最小限となるように金融機関も様々な経費を認めてくれます。
しかし、任意売却の費用負担が最小限で済むのは、競売開始決定前の話しとなります。
競売開始決定後は、「任意売却のハードルも一段と高く」なります。
当初は認めてくれた引越し代も、競売開始決定後は断られることも想定されます。
また、売却価格に関しても裁判所から公開される評価書を元に算出されるため、任意売却当初の価格から更に上がってしまうことも珍しくはありません。
任意売却時に持出し費用を最小限に抑えるには、競売開始決定前に任意売却で取引を終える必要があります。
実現するにはできる限り早めに相談し、行動する以外方法はありません。
任意売却を決断するなら早めがメリット大!
任意売却で不動産を売却した際の税金はかかるの?

お客様から多く寄せられるご質問の1つに、任意売却と税金に関する内容があります。
〈任意売却の税金の心配〉
- 不動産を売却するから税金がかかるのでは?
- 不動産を手放しても税金を払う余裕はない・・・
任意売却を含む不動産の売却で注意しなければならないのが、不動産を売却した際の「譲渡所得」です。
任意売却でも譲渡所得があれば課税されます。
不動産を売却して利益が出ると課税対象
不動産売却時の譲渡所得とは?
譲渡所得税とは、不動産を売却したとき「利益に対して課税」される税金のことです。
任意売却後に課税されるとしたら、この譲渡所得税となります。
厳密に言うと「所得税」と「住民税」であり、土地や建物等の不動産だけでなく、株式などの資産を譲渡したときに発生します。
譲渡所得税を説明する上で重要なのが、任意売却の売却価格ではなく、「売って得た利益」に課税されるという点です。
売却価格ではないので注意!
譲渡所得税の計算式
譲渡所得税=(売却価格 ー(取得費+譲渡費用))×税率
※ 取得費…不動産を取得した時にかかった費用、土地や建物の購入代金など
※ 譲渡費用…不動産を売却する時にかかった費用、仲介手数料など
※ 税率は不動産の所有期間により異なる
諸費用も含め不動産を買った金額「取得費」よりも、売ったときの金額がプラスになれば、「プラス分(利益)に課税」される仕組みです。
注意するポイントは取得費
前の項で触れた「取得費」については、注意して欲しいポイントがあります。
〈取得費の注意点〉
- 相続した不動産
- 建物の減価償却
不動産の所有者は、ご自身で購入した方ばかりではありません。
先祖代々相続で受け継いだ不動産は購入金額など、分からないこともあります。
また、先代が購入し売買契約書などから、当時の購入金額が判明しても、はるか昔のため「わずか数万円」のケースもあります。
売却価格が高額になれば、取得費がほぼ「¥0」と大差ありません。
売却金額のほぼ「全額が利益となり課税されるの?」
このような場合、売却価格の「5%」が取得費とされ、実際の取得費が5%以下となっても、概算取得費として5%までは認められます。
取得費として最低5%はOK!
建物の減価償却は要注意
少し話がややこしくなりますので、特に以下の該当者はよく注意して読み進めてください。
〈該当する方〉
- 相続した土地に建物を建てて売却した方
- 親の土地に建物のを建て、土地を相続後に売却した方
不動産の売却時に建物については、年々古くなるため減価償却するルールがあります。
例えば、以下の取得費を考えてみてください。
〈取得費は?〉
・土地(相続のため購入価格不明)
・建物(15年前に4,000万円で建築)
中古戸建として6,000万円で売却したら?
土地は購入金額が不明なため、5%の概算取得費としますが6,000万円の内訳として土地と建物の価格をそれぞれ決める必要があります。
また、建物の建築費4,000万円が取得費として、認められる訳ではありません。
建物の取得費については、減価償却されるため木造住宅で築後15年となると、その価値は約32%程度となります。
単純計算で「約1,280万円が取得費」となります。
〈建物の取得費は減価償却される〉
× 4,000万円
〇 約1,280万円
土地4,000万円・建物2,000万円での売却を仮定すると
〈6,000万円の取得費〉
土地4,000万円の取得費 200万円(5%)
建物2,000万円の取得費 1,280万円
取得費 合計1,480万円
相続した土地の場合、売却価格に対する取得費の割合が低くなる可能性があり、高額な譲渡所得税が発生するケースもあります。
特に建物の建築費は減価償却されるため、築年数が経過すると売却時には思ったほどの取得費とならないため注意しましょう。
ただし、マイホームの売却や任意売却の際は、特例もあり実際に譲渡所得税が発生するケースは限られていますので、続いて解説します。
マイホームの売却や任意売却は特例で非課税も
任意売却で譲渡所得税がかからないケースが多い理由

任意売却で課税される税金の種類に譲渡所得税がありますが、実際に譲渡所得税がかかるケースはほとんどありません。
〈課税されない訳〉
- 利益が出ないから
- 特別控除の特例が認められるから
- 強制換価等による特例が認められるから
※ 要注意ポイント有
それぞれの内容を詳しく解説します。
1.利益が出ないから
譲渡所得税は資産を売却したとき、得られる「利益に対して課税」される税金と既に解説しました。
任意売却では不動産そのものは売却できても、そこから売却益を得られるケースはほぼありません。
そもそも、売却価格を上回るローンがあり、不動産の購入時から債務超過の状態が続いてきた結果、任意売却に至るなど、無理な借入が原因でもある。
むしろ、売却後もローンの残債を返済し続けることが多いでしょう。
「利益が出ない」ため、任意売却をしても課税されません。
任意売却はオーバーローンが基本
2.特別控除の特例が認められるから
居住用財産、すなわちマイホームを売却するときは、譲渡所得から「最高3,000万まで控除できる特例」があります。
この特例は、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といい、所有期間に関わらず受けられるものです。
この特例を受けるにはいくつかの要件がありますが、それらをクリアすれば任意売却でも適用されます。
3,000万円以上の売却益を出せるケースはそう多くありませんので、譲渡所得税がかかることはほとんどないと言えるでしょう。
なお、マイホーム以外の不動産(家族や親族名義のもの)や別荘などは特別控除の対象から除外されます。
自宅の任意売却であれば、3,000万円の特別控除によって課税されるケースは少ないのが実情です。
3,000万円の特別控除は大きなメリット
3.強制換価等による特例が認められるから
任意売却や競売では「強制換価等による特例」が認められます。
資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における国税通則法第二条第十号(定義)に規定する強制換価手続による資産の譲渡による所得その他これに類するものとして政令で定める所得(第三十三条第二項第一号(譲渡所得)の規定に該当するものを除く。)
引用元:所得税法第9条第1項10号
強制換価等による譲渡(第10号関係)
この特例は、返済能力がないために借金を返すための資金を調達できない場合に適用されます。
そのため借金の返済など、やむを得ずに不動産を売却する際、売却代金が借金の返済で手元に残らなければ課税されずに済みます。
任意売却や競売では、多くの方が該当するのではないでしょうか・・・
それでも「強制換価等による特例」について、任意売却を希望される場合には「要注意ポイント」があります。
なぜなら、本来ならば任意売却後に譲渡所得税が課税されるケースで、「強制換価等による特例」により非課税となるには、売却代金のすべてを債務の返済に充てることが要件となっています。
もちろん、売却に必要となる諸費用は控除できますが、ここで問題となるのが「引越し代を受領した」場合です。
この特例を利用できない可能性が高い!
任意売却時の引越し代は、金融機関から受け取る訳ではありません。
売却代金の中から金融機関が「引越し代」として回収しないで残してくれた金銭となります。
従いまして、正確に表現すると売却代金の諸費用を除いた全額を金融機関に返済するのではなく、一部を引越し代として残すことになります。
その結果、「強制換価等による特例」の要件を満たさない可能性があるからとなります。
不慣れな業者は認識不足のリスク大!
任意売却した年の固定資産税はどうなるの?

任意売却時の固定資産税は、決済時(引渡し日)までの日割りで精算されます。
固定資産税は毎年1月1日時点での登記名義人に納税義務があります。
そのため固定資産税を納付するのは売主であり、不動産取引の慣例で以下のように日割りで精算します。
売主は引渡し日前日までの固定資産税額を負担し、買主は引渡し日以降の固定資産税額を負担します。(買主は「固定資産税精算金」として売主に支払う)
よって、任意売却をした年は、売主に固定資産税を納付する義務があります。
※ 固定資産税の滞納により、不動産が差押えの登記がなされていれば、滞納を解消しなければ任意売却は成立しません。
1月1日の登記名義人に納税義務
まとめ

任意売却をしたからといって、何か特別な税金がかかることはありません。
基本的には通常の不動産売却と同じように手続きを進めていくので、手続きにかかる費用も相場とほぼ同じです。
資金に余裕がない中でお金のことを考えると苦しい気持ちになりますが、ローンや税金の滞納問題はできるだけ早く解決すべきです。
特に任意売却にはリミットがあり、手続きが遅れると競売で自宅を強制的に失う可能性もあります。
当事務所は、一人ひとりのお客様に合わせた最善の方法をご提案できます。
住宅ローンの滞納や競売などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
あわせて読みたい

住宅ローンが苦しくて任意売却をスタートすると気付く大切なこと
自宅の任意売却をスタートする方は、大きく分けると2つに分類されます。 1つは住宅ローンが既に払えなくなっている方、もう1つは生活は苦しいけれど、まだ住宅ロー...