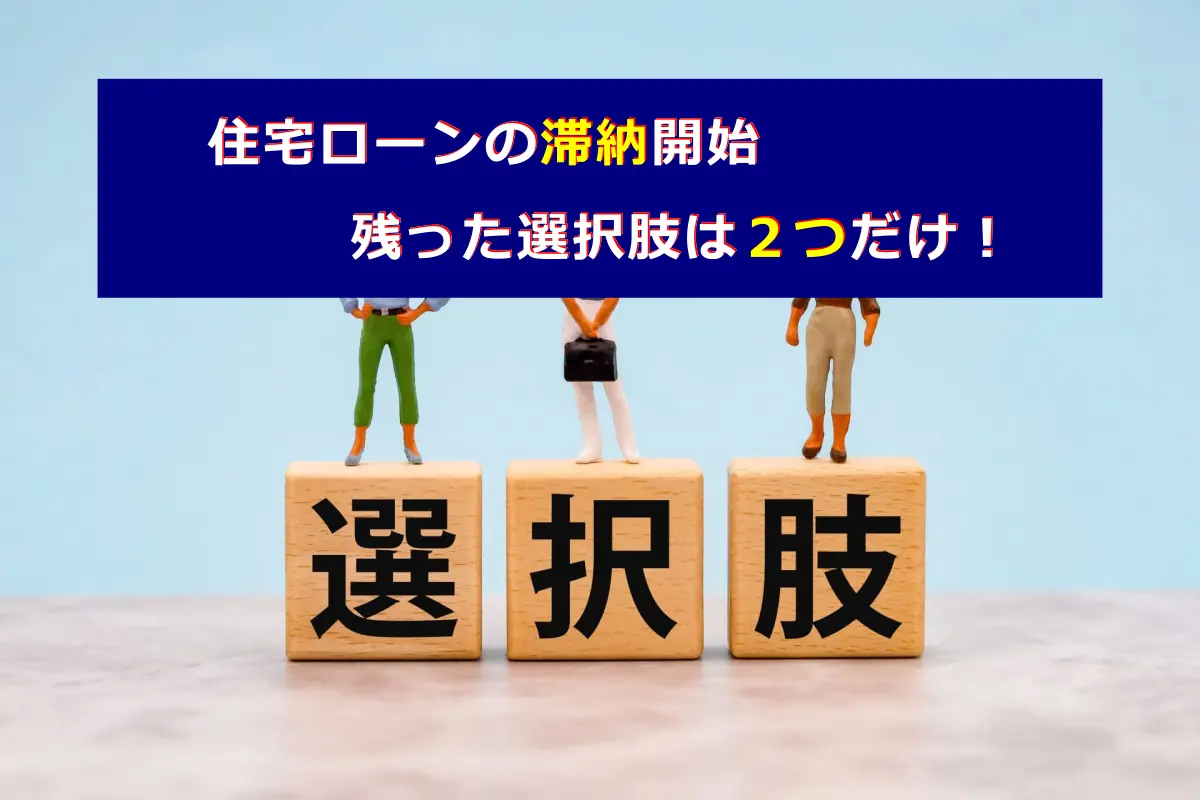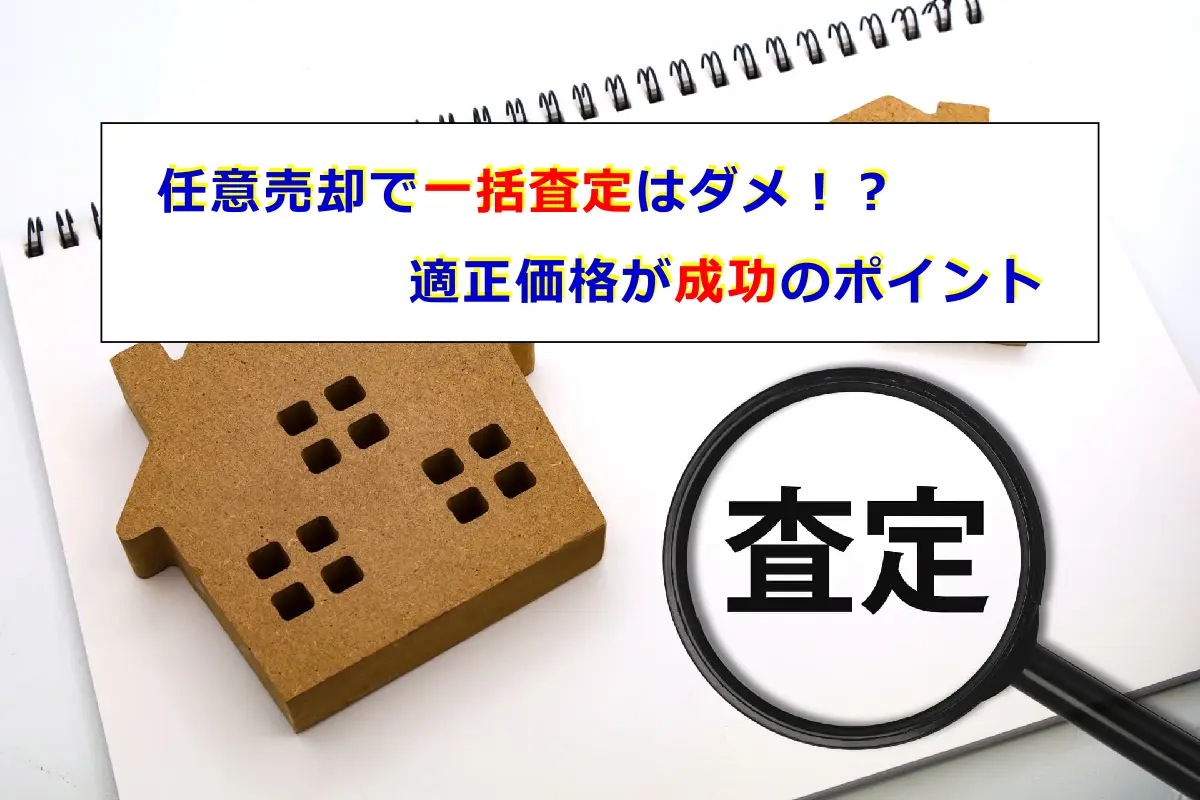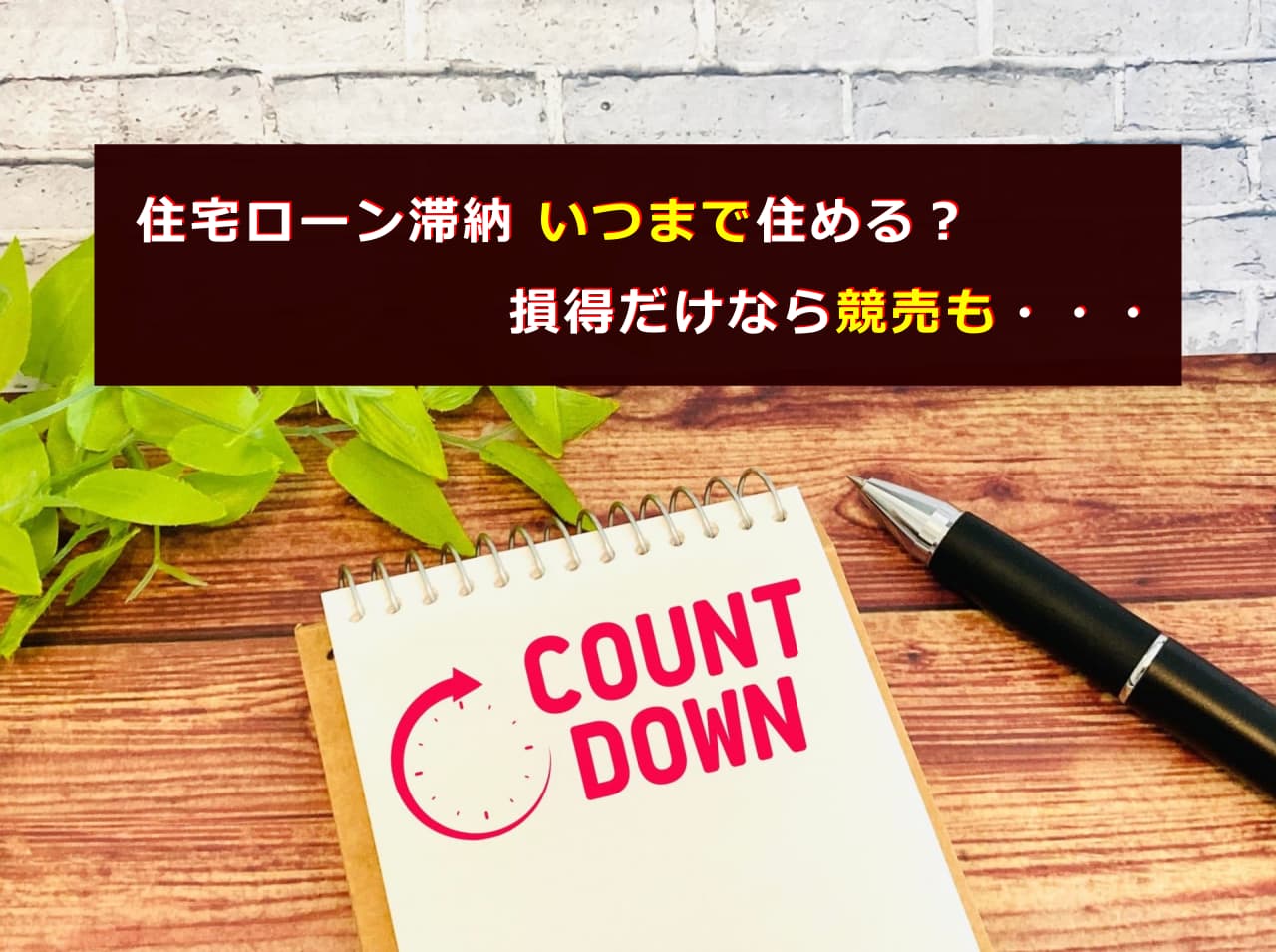土日祝日も受付中
債権譲渡とは|住宅ローンを例にわかりやすく解説

借金の返済が困難になり、滞納を続けると金融機関は「債権を第三者へ譲渡」することがあります。
住宅ローンの滞納を例にあげると、任意売却や競売などの方法で不動産を処分して、借金を返済するのが一般的です。
しかし、任意売却や競売を以っても、ローンを全額返済できる訳ではありません。
この場合、債権譲渡によって残債が第三者へ売却されるケースが多くなります。
過去に不良債権の回収に携わったFP&不動産コンサルの有資格者が「住宅ローンの滞納を例に債権譲渡について」まとめました。
債権譲渡の目的や債権譲渡が行われた際に、注意すべきポイントを解説します。
事業者が利用する「不動産担保ローン」も仕組みは同様ですので、参考にしてください。
目次
債権譲渡とは

債権譲渡をひと言で説明すると、債権者の意志で「債権を第三者に移転」させることをいいます。
住宅ローンに例えると
AさんがB金融機関で3,000万円の住宅ローンを借りる
残債が2,000万円になったところで返済がストップ
B金融機関は「Aさんに2,000万円の返済を請求する権利」をC社に譲渡
※ B金融機関が「譲渡人」 C社が「譲受人(サービサー)」
上記の例「B金融機関 → C社」の流れが債権譲渡となります。
譲渡という言葉には「譲り渡す」というイメージがありますが、債権譲渡の場合は債権を第三者に「売却」するという理解が適切です。
借金が他人に売却されること
債権譲渡の目的は?
債権譲渡は、主に金融機関が早期に不良債権を処理する目的で行われます。
住宅ローンのような高額で返済期間の長いローンは、ケガや病気、リストラなどさまざまな事情で返済が困難になる事態が想定できます。
住宅ローンの滞納は、債権者である金融機関にも損失を与えます。
その際、金融機関は第三者へ売却して「早期に不良債権を処理」しようと考えるのです。
迅速に不良債権の処理が原則
債権譲渡のタイミング
不良債権の処理で債権譲渡されることは理解できても、その時期がいつになるのか?
大変気になると思います。
住宅ローンの返済が滞り金融機関がサービサーへ債権譲渡する場合、2つの違いによってタイミングが異なります。
その違いとは、担保ありの債権(以下、有担保債権)・担保なしの債権(以下、無担保債権)の2つに分かれます。
〈債権の違い〉
- 有担保債権(不動産などの担保がある)
- 無担保債権(担保が無い、あるいは担保の処分済み)
有担保債権か、無担保債権かによって、サービサーへ債権譲渡される時期や対処法が異なります。
住宅ローンを滞納中の方は、違いをしっかり理解しましょう。
有担保と無担保では全く異なる
有担保債権:債権譲渡のタイミング
担保となる不動産を処分(売却)せず、そのまま「担保付きでサービサーへ債権譲渡」してしまいます。
このケースは、ネット銀行等の保証会社を利用しない金融機関が主に行います。
住宅ローンの滞納が始まると「期限の利益の喪失後」、速やかに債権譲渡されてしまいます。
期限の利益の喪失について詳しく
あわせて読みたい

期限の利益の喪失で住宅ローンはどうなるの?
住宅ローンを滞納したら「期限の利益喪失予告書が届いたけど」、どうすれば・・・ 「期限の利益の喪失」の意味が、分からない? 住宅ローンの返済が滞ると、金融機関...
いわば不良債権のスピード処理となりますので、任意売却を希望されるなら債権譲渡後のサービサーと交渉するケースが多くなります。
譲受人が担保の処分!
あわせて読みたい

任意売却の契約後にサービサーへ債権譲渡された!
最近では、ネット銀行の住宅ローンが人気です。 一見すると保証料が無いなど、諸費用も少なく済むケースや金利の低さもあり、大変魅力的です。 ただし、借りてしまえ...
無担保債権:債権譲渡のタイミング
担保となる不動産は任意売却あるいは、競売で先に処分(売却)してしまいます。
そして、完済できなければ「残債をサービサーへ債権譲渡」となります。
有担保債権
↓
担保の処分
↓
無担保債権
↓
債権譲渡
※ 消費者金融やカードローンのように、もともと無担保の債権は除外してください。
保証会社を利用した住宅ローンの場合、保証会社が「代位弁済後」に担保の処分を済ませます。
代位弁済について詳しく
あわせて読みたい

代位弁済されたら住宅ローンは保証会社から請求される
民間金融機関で住宅ローンを借りるとき、原則として連帯保証人は不要ですが、保証会社との契約が必要となります。 民間金融機関とは、皆さんが街中でよく目にする「銀...
その後、無担保債権となった残債をサービサーへ債権譲渡する流れが一般的です。
主に街中で目にする銀行やメガバンク、信金等の住宅ローンが該当します。
有担保のまま債権譲渡される場合と比較して、担保を先に処分するため時間を要します。
ただし、担保の処分後に残債がある場合に限られるため、完済できていれば債権譲渡されずに済みます。
有担保 → 無担保 → 債権譲渡
あわせて読みたい

逃げた債務者の探し方!サービサーや金融機関はどうやって見付けるの?
任意売却は無事終了しても、残った住宅ローン(残債)をどうするか? 本当に悩んでいる方も多いと思います。 また、残債のことを考え、任意売却の前に自己破産を検討...
債権譲渡をされたらどうなる?
債権譲渡をしても、債権の内容や条件自体は変わりません。
では、何が変わるのか?
返済先が、「金融機関(譲渡人)から債権回収会社(譲受人)」に変わるという点です。
住宅ローンに例えると
AさんがB金融機関で住宅ローンを借りて滞納
B金融機関がC社に債権譲渡
AさんはC社に対して返済義務
※ B金融機関が「譲渡人」 C社が「譲受人(サービサー)」
債権譲渡が行われたからといって、Aさんが特別な手続きをする必要はありません。
また、債権譲渡によって借金が増えたり減ったりすることもありません。(利息や遅延損害金は発生します)
債権譲渡の際は、譲渡人である金融機関から「債権譲渡通知書」が届きます。
債権譲渡通知書が届いたら?
債権譲渡通知書が届いたら、速やかに対処すること。
住宅ローンの場合は金額が大きく、一括返済は難しいため、専門家に相談することをおすすめします。
借金の減額や返済免除については弁護士へ、自宅の売却に関しては、任意売却に精通する業者が手馴れています。
あわせて読みたい

遅延損害金とは|利率や計算方法、免除の方法などを解説【住宅ローン】
住宅ローンを滞納すると、気になるのが遅延損害金の存在です。 遅延損害金とは、約束の期日までに住宅ローンの返済が行われなかった時に発生するペナルティのことです。...
債権管理回収業は誰でもできる?
債権管理回収業は、誰にでもできる訳ではありません。
債権管理回収業として営業するには、申請書や必要書類を提出して「法務大臣の許可」を得る必要があります。
当初、債権管理回収の業務は弁護士、または弁護士法人のみに許可されたものでした。
しかし、バブル崩壊後に不良債権が急増したことを受け、その処理に他の民間企業の力が必要となりました。
その結果として、平成10年に公布された新たな法律が「債権管理回収業に関する特別措置法」(いわゆるサービサー法)です。
この法律によって、弁護士だけでなく民間業者も「サービサー」として債権管理回収業務を行えるようになりました。
債権管理回収業務で譲受人となるには、法務省が定める条件をクリアしなければなりません。
具体的な条件の例をいくつかピックアップしました。
〈サービサー認可の条件〉
- 株式会社であること
- 資本金が5億円を下回らないこと
- 業務を公正に実行できる知識と経験をもつ弁護士がいること
- 暴力団員等が関わっていないことなど
あわせて読みたい

サービサーとは|住宅ローンを例に債権回収の経験者が解説
債務者が借金の返済に応じない場合、金融機関などの債権者に代わって「サービサー」と呼ばれる会社が債権回収を行う場合があります。 「金融機関などが債権譲渡を行っ...
無許可業者による委託での債権回収は違法
債権管理回収業には、金融機関などの債権者から委託を受けて債権を回収するケースもあります。
債権回収を委託を受けて行うには、法務大臣の許可が必要です。
サービサー以外の民間企業が委託での債権回収は違法
そもそも委託による債権回収は、本来ならば弁護士以外は行えません。
債権回収業者(サービサー)が行えるのは、弁護士法の特例として認められているからです。
実のところ、国の許可を受けていない業者による架空請求が数多く報告されています。
実在する債権回収会社に似た名前で相手を信用させ、法外なお金を取られたという被害もあります。
悪徳業者による架空請求については、法務省も注意喚起をしています。
法務大臣が許可した債権回収会社(サービサー)はこちらから確認できます。
身に覚えのない業者から請求があっても、即座に応じてはいけません。
まずは、許可を得た会社かどうかを確認することが大切です。
本当のサービサーなら回収にも手順を踏む
あわせて読みたい

保証協会サービサー(保証協会債権回収株式会社)とは
借金の滞納を続けると、貸し手の金融機関に代わってサービサーが債権回収を担うことがあります。 サービサーと聞いて「怪しい会社では?」「取り立てられるのが怖い」と...
債権譲渡のメリット

債権譲渡は金融機関が債権を回収する目的で行われるもので、借金を返済する側に大きなメリットはありません。
一方、金融機関側には次のようなメリットがあります。
〈債権譲渡:金融機関のメリット〉
- 貸倒れの経理処理
- 不良債権をスピーディに現金化
- 債権管理コストの削減
住宅ローンを例にあげて金融機関が債権譲渡を行う上でのメリットを解説します。
メリット1.貸倒れの経理処理
こちらは主に、ネット銀行やプロパー融資等の保証会社を利用しない場合、有担保債権の債権譲渡が該当します。
住宅ローンの返済に応じてもらえない場合、「金融機関は貸倒れとして経理処理」が必要です。
しかし、経理上のルールから住宅ローンのように担保がある場合、担保の処分後でなければ貸倒れによる損金経理ができません。
そのため有担保のまま債権譲渡することにより、早々に経理処理が行えることは金融機関にとっては大きなメリットになります。
早期に経理上の処理ができる
メリット2.不良債権をスピーディに現金化
住宅ローンの滞納後、強制執行がはじまるまでには数ヶ月ほど時間がかかるのが一般的です。
滞納を続けるということは、金融機関が本来受け取れるはずだった貸付金を回収できません。
ローンを返済する側が大変な思いをするのと同じで、金融機関もまた不良債権は早々に処理することを望んでいます。
債権譲渡であれば、金融機関の希望するタイミングで不良債権を売却できます。
不良債権の債権譲渡を想定すると
金融機関の住宅ローン残債1,000万円
→ サービサーへ900万円で債権譲渡(売却)
→ 金融機関は100万円の損失
金融機関自ら回収となると、任意売却を待つには時間が掛かります。
また、競売となれば更に時間も費用も必要となります。
不良債権となった時点で債権譲渡してしまえば、損失は出ても「早期に現金化できる」ため、金融機関にとっては大きなメリットとなります。
こちらもメリット1同様に、有担保債権の債権譲渡が該当します。
早期に現金化は何よりも重要
あわせて読みたい

2番抵当のサービサーが競売に取下げはできる?
今回は「自宅を2番抵当のサービサーから競売の申立てをされてしまった」会社経営者(Aさん)からの相談をご紹介します。 Aさんの希望は言うまでもありません、競売の...
メリット3.債権管理コストの削減
金融機関にとって不良債権を回収するには、それなりの管理コストが掛かります。
特に、住宅ローン等の担保を処分した後の不良債権(無担保債権)を管理し続けるのは、回収の見込みが少ない割に多大なコストが必要となります。
そのためはるか昔は、この様な不良債権は数年後は債権放棄して、残債を請求しなくなることが多くありました。
しかし、現在で不良債権をまとめサービサーへ売却(債権譲渡)し、管理コストの削減させるのが主流となっています。
無担保債権の管理コストについて、もう少し付け加えるならば、消費者金融やカードローンを思い浮かべてください。
こちらについては、住宅ローンなどと比較してかなりの高金利となります。
その意味は貸付金が少ないこともありますが、借手の信用度も低くなります。
一旦、返済が滞ってしまえば、信用度の低い方から回収するのは大変なことです。
いわば、管理コストが掛かるため、高金利でなければ成り立たないのです。
同様の意味合いで、有担保債権から無担保債権となった場合、その借手の信用度は低く(なってしまった)、継続的に回収していくには管理コストが見合いません。
その他、サービサーの購入金額もわずかではありますが、不良債権が現金化できるため、多少のメリットと言っても差し支えないでしょう。
無担保債権の管理コストは消費者金融と同程度
債権譲渡の対抗要件について

住宅ローンにおける債権譲渡は、ローンの契約者と金融機関、そして債権回収会社の三者が関与します。
私法では、三者が互いに権利を主張し合うことを「対抗する」と表現し、対抗するために必要な条件を「対抗要件」といいます。
対抗要件には①債務者に対するもの②第三者に対するものと2種類があるので、ここからはその違いを見ていきましょう。
種類①債務者への対抗要件
債権譲渡の際は、債権者は債権が第三者へ譲渡されたことを債務者に対して通知する必要があります。
例えば
住宅ローン滞納中のAさん
住宅ローンを貸したB金融機関が債権譲渡
B金融機関は債権譲渡をAさんに通知
通知がする理由は、債務者であるAさんへの対抗要件を満たすためです。
Aさんが債権譲渡が行われた事実や新しい債権者を把握していなければ、契約通り返済が行われない可能性があります。
仮に対抗要件を満たさないまま債権譲渡が行われたとしても、新しい債権者となるC社はAさんに対して権利を主張できないのです。
ただし、通知が無くても債務者であるAさんが債権譲渡を承諾すれば有効となります。
譲渡人から債務者へ通知で有効
種類②第三者への対抗要件
対抗要件を満たすには、第三者への通知も必要です。
債権譲渡は債務者の同意なく行えるため、譲渡後は複数の譲受人が存在することもあり得ます。
債権譲渡が二重に行われた場合、その権利を主張する者の優劣を決定するのが第三者への対抗要件です。
複数の債権者がいると誰が正式な権利者であるかがわかりにくく、債務者の混乱を招きます。
また、悪意のある債権者が二重譲渡するケースも過去に発生しました。
対抗要件と成立要件の違い
互いの権利を主張するのに必要な条件を対抗要件といいます。
これに対して、契約そのものを成立させるために満たすべきもののことを「成立要件」といいます。
成立要件は、契約への申し込みと、それを承諾したという意思表示のもとに成り立つものです。
法律行為を成立させるために必要な条件です。
成立要件がなければ「契約自体が成立しない」ことを意味します。(成立要件を満たさなければ、その契約については法律効果も発揮しません)
最悪の場合、権利のない者へ返済するといった事態も想定できます。
債務者を守るという意味でも、「第三者への対抗要件が必要」となります。
〈第三者への対抗要件は2つ〉
- 譲渡人から債務者への通知
- 債務者の承諾
共に「確定日付のある証書」であること
重要なポイントは、「種類①債務者への対抗要件」にプラスして「確定日付のある証書」でなければ第三者へ対抗できないことです。
確定日付のある証書で債務者が承諾となると、あまり現実的ではありません。
一般的には、債権譲渡通知を「内容証明郵便で送る」ことで有効となります。
債権譲渡登記制度について

債権譲渡登記は、その名の通り債権を譲渡したとき、必要となる手続きのことです。
登記とは
個人や法人の権利を守り、取引を円滑に行うために定められている制度のこと。
よく目にするのが「不動産登記」で、建物の所在地や大きさ、所有者をまとめて社会に公示することを目的とする。(おもに新築・中古物件の購入時や、未登記建物の表題登記の際に必要となる)
債権譲渡登記制度を活用するメリットは、第三者への対抗要件を簡易に備えられる点です。
債権の流動化など、法人の資金調達手段が多様化したことをきっかけに、対抗要件を備える仕組みが創設されました。
債権譲渡禁止特約の効力について

旧民法では、債権者と債務者の間で「債権譲渡禁止」の契約を取り交わすと債権は譲渡できないというルールがありました。
これは、債権が知らない間に第三者へ譲渡されることで契約を交わした意義が失われてしまうのを防ぐためです。
しかし、2020年の民法改正では、債権譲渡禁止特約をした場合でも債権を譲渡できることが決定しています。
第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
引用元:改正民法第466条2項
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
もっとも、債権譲渡後も悪意のある譲受人(新しい債権者)に対しては弁済を拒むことができます。
これによって悪徳な業者からの架空請求は回避できるので、債務者が不利益を被るリスクは少ないといえるでしょう。
債権は財産
この記事では、住宅ローンなどの不動産担保ローンが、不良債権化したあとの債権譲渡について書いています。
そのため、特に無担保債権については、ほぼ価値が無いかのように感じるかもしれません。
しかし、本来は無担保でも有担保でも、どちらの債権も貸手側から見れば請求できる権利に変わりは無く「財産」として、みることができます。
債権譲渡を単純に考えれば、財産(債権)を持つものが、第三者へその財産を売却することです。
債務者(借手)側からすれば、貸手が変わっただけで特別なことはありません。
債権譲渡は特別なことではない
任意売却は債権譲渡の可能性を考慮し専門の業者に相談しよう

任意売却後に残った債務は債権譲渡されるケースが多いです。
債権譲渡後は、債権回収会社(サービサー)が返済を求めてきます。
当然ながら債務者には返済義務がありますが、任意売却をした状況では生活に余裕がないことがほとんどです。
債権回収会社は借金回収のプロですから、返済能力のない債務者からお金を回収するのが難しいことを理解しています。
そのような状況下だと、交渉次第で大幅な減額が可能となる場合もあります。
債権譲渡の可能性も含めて、任意売却を検討する際は経験豊富な業者へに相談することが大切です。
住宅ローンが払えなければ早めに相談を!
あわせて読みたい

任意売却後の残債はどうすれば?競売は残債を請求されないの?
住宅ローンを含む不動産担保ローンが払えなくなったら、任意売却で対処するのは貸手(債権者)と借手(債務者)の双方にとって合理的な手段です。 しかしながら、任意...