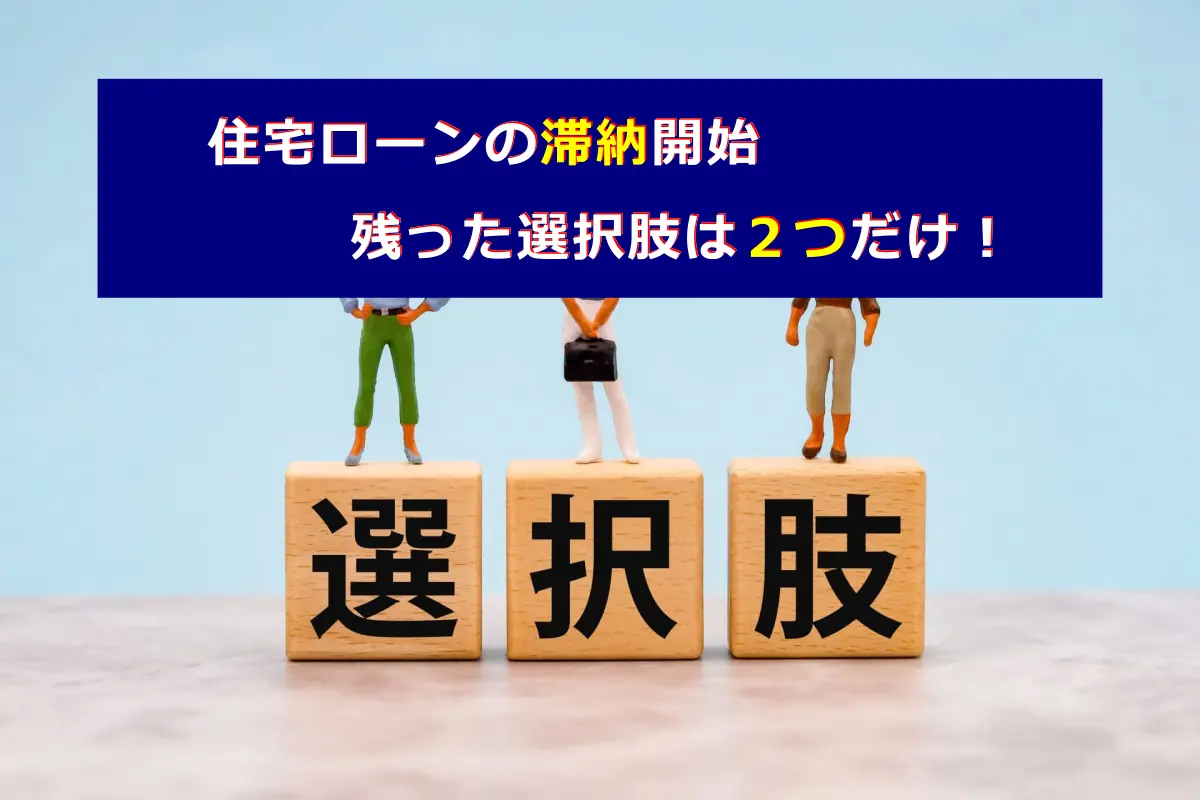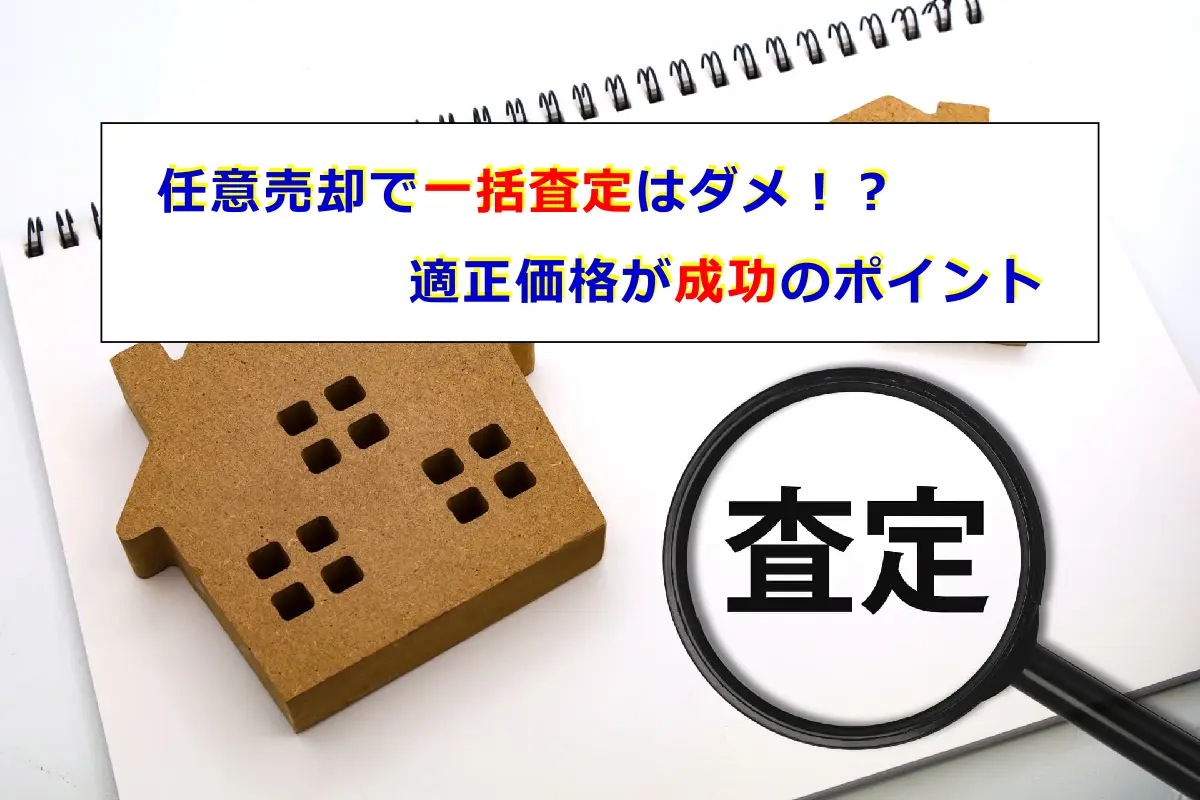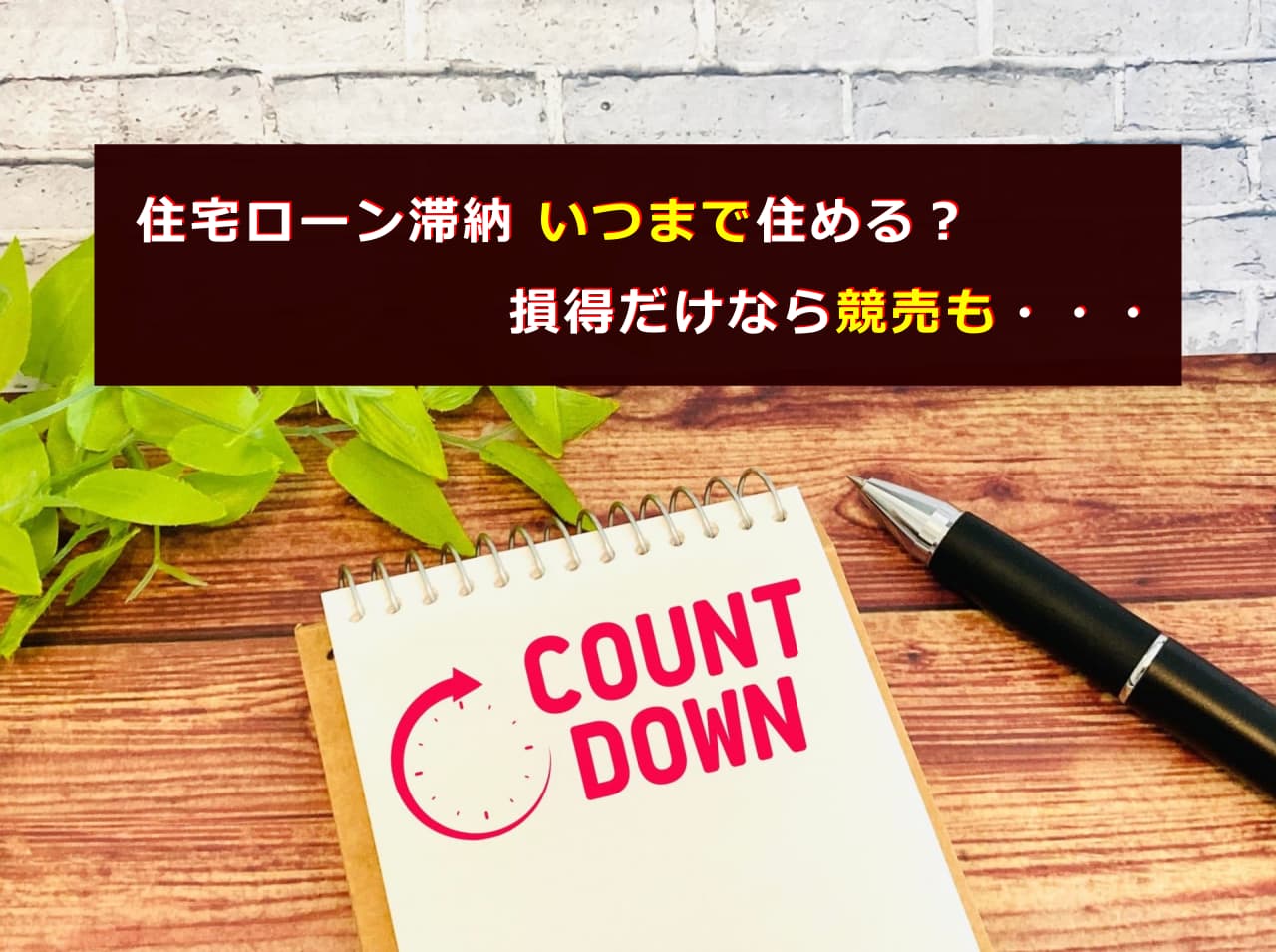土日祝日も受付中
根抵当権のある任意売却は極度額にも要注意!

不動産を担保にお金を借りるとき、不動産の登記事項には抵当権が設定されます。
その抵当権の一種である根抵当権には、旧制度(以下、旧根抵当権)がありました。
任意売却で10年以上のキャリアのある方なら、ご存知の方が多いと思いますが、現在の根抵当権と旧根抵当権では「極度額に違い」が生じます。
旧根抵当権の後に根抵当権(後順位)の設定があった場合、正しく理解していないと任意売却の配分を巡り大きなトラブルになりかねません。
もう、制度も変わっているため実務上も遭遇する機会も減っていますが、該当者の参考程度になればと思います。
3代続く企業など古くから金融機関と取引している場合、少し注意してください。
FP&不動産コンサルの有資格者が、今では珍しくなった「旧根抵当権」と「根抵当権」との違い、そして「抵当権」についても合わせて解説します。
目次
旧根抵当権は遅延損害金の回収額が異なる
不動産を担保にお金を借りると、金融機関は不動産に抵当権の登記をしますが、根抵当権の場合は「極度額」という項目も記録もされます。
不動産の登記事項を確認し、根抵当権に「元本極度額」や「債権元本極度額」の記載があり、任意売却を検討中ならば要注意です。
それは現制度の根抵当権とは異なり、「旧根抵当権」を意味しています。
注意が必要な理由として、2番抵当や3番抵当等の後順位の抵当権者がいる場合、任意売却時の回収額が大きく変わる可能性があるからです。
不動産担保ローンの借手が返済不能に陥れば、金融機関は競売や任意売却で回収します。
その際に「遅延損害金が発生」すると、2番抵当など後順位の抵当権者は、どうなるでしょうか?
あわせて読みたい

遅延損害金とは|利率や計算方法、免除の方法などを解説【住宅ローン】
住宅ローンを滞納すると、気になるのが遅延損害金の存在です。 遅延損害金とは、約束の期日までに住宅ローンの返済が行われなかった時に発生するペナルティのことです。...
当然、遅延損害金が多ければ、その分は後順位の抵当権者の回収額が減る可能性があります。
その上で現在の根抵当権と旧根抵当権を比較すると、更に受取れる回収金額が減る可能性があります。
2番抵当や3番抵当は要注意
あわせて読みたい

2番抵当,3番抵当でも任意売却は諦めずに相談を!
住宅ローンでもリフォームローンなどの追加により、不動産に2番抵当が設定されていることは珍しくはありません。 とりわけ自営業の方や中小零細企業が利用する事業用...
根抵当権と旧根抵当権の違い
競売や公売など強制的に不動産が処分されてしまう際、優先して受取れる根抵当権の極度額に違いが生じます。
端的に示すと極度額に「遅延損害金を含めて計算する・しない」の違いです。
登記事項に「元本極度額」や「債権元本極度額」とあれば、元金についての極度額となります。
旧根抵当権の場合、遅延損害金を合わせ極度額を超えてしまっても、優先して2年分の遅延損害金も受取れます。
これに対して根抵当権は、元本と遅延損害金の合計が、極度額を超えてしまうと極度額までしか受取れません。
〈競売時の極度額の違い〉
- 根抵当権
元金+遅延損害金(2年分) 極度額 - 旧根抵当権
(元金 極度額)+遅延損害金(2年分)
根抵当権と旧根抵当権の違いは、競売を例にすると分かりやすいと思います。
それでは以下の条件で競売となり、根抵当権と旧根抵当権の落札後のシュミレーションをしますので、回収額がどのようになるのか見てみましょう。
〈競売時・根抵当権と旧根抵当権の回収額の違い〉
- 落札価格 :1,280万円
- 1番抵当
根抵当権 :元金1,000万円・極度額1,200万円
旧根抵当権:元金1,000万円・元本極度額1,200万円 - 2番抵当 :元金100万円
- 延滞期間 :2年以上
| 根抵当権 | 旧根抵当権 | |
| 遅延損害金(年14%) | 280万円 | 280万円 |
| 債権総額 | 1,280万円 | 1,280万円 |
| 回収可能額 | 1,200万円 | 1,280万円 |
| 2番抵当回収額 | 80万円 | 0 |
・元金(1,000万円)と遅延損害金(280万円)は根抵当権と旧根抵当権は共に同条件のため債権総額も同じです。
続いて順番に見ていきましょう。
根抵当権
現行の根抵当権は、元金と遅延損害金の合計が1,200万円を超えてしまいます。
元金1,000万円+遅延損害金280万円 極度額1,200万円
極度額を80万円オーバーしているため2番抵当へ配当が回る
極度額の1,200万円が回収額の上限となります。
2番抵当は80万円回収できます。
根抵当権の極度額 元本と遅延損害金
旧根抵当権
旧根抵当権は元金が元本極度額の1,200万円を超えていません。
元金1,000万円 元本極度額1,200万円+遅延損害金280万円
元金が極度額以内、遅延損害金280万円も回収、2番抵当への配当無
2年分の遅延損害金を合わせて1,280万円回収可能です。
その分、2番抵当までは配当が回らず回収額は¥0となってしまいます。
旧根抵当権の極度額=元本の上限+遅延損害金
任意売却時の旧根抵当権の扱い
登記事項に元本極度額や債権元本極度額の記載があると旧根抵当権となり、それは文字通りで元本(元金)の極度額になります。
先に説明した競売時のシュミレーションは基本的に任意売却の場合も、この原則で債権者に配当します。
つまり、任意売却する場合も通常の根抵当権とみなさず、遅延損害金は別で計算しなければなりません。
そのため、任意売却時に1番抵当が旧根抵当権の場合、元本が極度額を超えていなければ遅延損害金も別に2年分を優先して配当、2番抵当以下には残りが配当されます。
後順位の抵当権者に厳しい、この旧根抵当権は最近は、ほとんど見ることは無いと思います。
ただし、昭和40年代の根抵当権が残っていた場合は、よく注意して下さい。
旧根抵当権は任意売却も競売の配当ルールに従う
あわせて読みたい

ハンコ代でしくじり?任意売却に不慣れな業者の珍配当案!
任意売却の取引において、しばしば「ハンコ代」と呼ばれる金銭のやり取りが生じるケースがあります。 任意売却で「ハンコ代」が必要となるのは、住宅ローンを含む不動...
抵当権とは?
せっかくなので、抵当権についても少し説明しましょう。
不動産を担保にお金を借りるとき、お金を貸した側が担保に取ることとは、具体的には不動産に抵当権の登記をすることになります。
その効果として、お金を貸した側は万が一返済が滞った場合、有利に働きます。
裁判所へ競売の手続きを済ませれば、強制的に不動産を売却し、その代金を回収することができます。
ここまでは、抵当権も根抵当権も同じです。
根抵当権と比較して大きく違うのは、抵当権は一度貸付けたあと、返済が終われば取引が終了します。
再び、同じ金融機関から不動産を担保にお金を借りるには、再度、抵当権の登記が必要になります。
他の金融機関から、新たに借りるのと同程度の手続きが必要です。
ちなみに住宅ローンのほとんどは、この抵当権となります。
抵当権は完済で取引終了
根抵当権と抵当権の違い
根抵当権は一度、不動産に根抵当権の担保設定をしておけば、登記された極度額の範囲内で、お金を借りたり、返済したりと繰り返し取引が可能です。
事業者が運転資金等で利用するには、大変融通が利きます。
一度、返済してしまうと取引が終了する抵当権とは違い、貸し借りの度に登記をする必要がありません。
ポイントは「元金+利息及び損害金等も含めて、極度額の範囲内」までが担保されます。
そのため、1,000万円を根抵当権の極度額とした場合、元金の貸付は700万円程度となります。
残りの枠は返済が滞った場合、遅延損害金も含め回収できるように備えている金融機関が多いように見て取れます。
極度額まで融資を繰り返せる
あわせて読みたい

自営業者の自宅兼事務所や多額の借入も任意売却は可能なの?
自営業の方や中小零細企業でも事業継続のためには資金調達も避けて通れないものです。 そして、経営者が自宅に事務所スペースや作業場を併設した建物に居住しているケ...
根抵当権と抵当権の競売時の違い
抵当権と根抵当権では、万が一焦げ付き競売となった際、やはり違いがあります。
担保となっている不動産を競売で処分したとき、受け取れる回収額が根抵当権は極度額の範囲内でした。
抵当権の場合、競売落札後の回収額はどうなるの?
先に上で紹介した根抵当権と旧根抵当権を比較した落札後のシュミレーションに抵当権も入れてみます。
競売時・抵当権・根抵当権・旧根抵当権の回収額の違い
- 落札価格 :1,280万円
- 1番抵当
抵当権 :元本1,000万円
根抵当権 :元本1,000万円・極度額1,200万円
旧根抵当権:元本1,000万円・元本極度額1,200万円 - 2番抵当 :元本100万円
- 延滞期間 :2年以上
| 抵当権 | 根抵当権 | 旧根抵当権 | |
| 遅延損害金(年14%) | 280万円 | 280万円 | 280万円 |
| 債権総額 | 1,280万円 | 1,280万円 | 1,280万円 |
| 回収可能額 | 1,280万円 | 1,200万円 | 1,280万円 |
| 2番抵当回収額 | 0 | 80万円 | 0 |
・元金(1,000万円)と遅延損害金(280万円)は抵当権・根抵当権・旧根抵当権、それぞれ同条件のため債権総額も同じです。
抵当権には極度額が無いため、元本とキッチリ2年分の遅延損害金も回収できます。
この点は、むしろ旧根抵当権であっても、元本が極度額を超えてなければ抵当権の回収額と実質同様となります。
〈抵当権・根抵当権・旧根抵当権のポイント〉
- 抵当権 元金+遅延損害金(2年分まで)を回収可能。
- 根抵当権 元金+遅延損害金(2年分まで)を極度額を上限に回収可能。
- 旧根抵当権 元金は極度額を上限+遅延損害金(2年分まで)を回収可能。
任意売却の実務でも、基本は上記のルールで取引することは先に書いた通りです。
あわせて読みたい

競売回避の方法をFP&不動産コンサルの有資格者が解説
住宅ローンの返済が滞ると、金融機関は回収のために裁判所へ不動産競売の申立てを行います。 競売は強制力のある措置なので、落札者が落札代金を支払えば不動産の所有...
抵当権と根抵当権で登記記録の違いは?
根抵当権は登記事項に極度額の記載があります。
旧根抵当権は登記事項に元本極度額や債権元本極度額が記載されると上で書きました。
登記記録からは極度額以下の貸付であることは想像できます。
しかし実際には、具体的な金額でいくら貸付されたのかは確認できません。
借入金額が分かってしまう?
その点、抵当権は貸付けた金額そのものが登記されますので、登記記録を確認すれば一目瞭然です。
そのため、登記記録から『あの人は住宅ローンを○○〇万円借りている』なんてことも分かってしまいます。
ただし、借りた金額のみで根抵当権同様に実際のローン残高がいくら残っているかは、登記記録を見ただけでは分かりません。
抵当権は借りた金額が分かる
あわせて読みたい

登記事項全部証明書から任意売却は推測できる
登記事項全部証明書から任意売却は推測できる 過去に競売の申立て3回、その内1回は取下げ(任意売却の可能性)他2回は競売で落札された1棟マンションです。