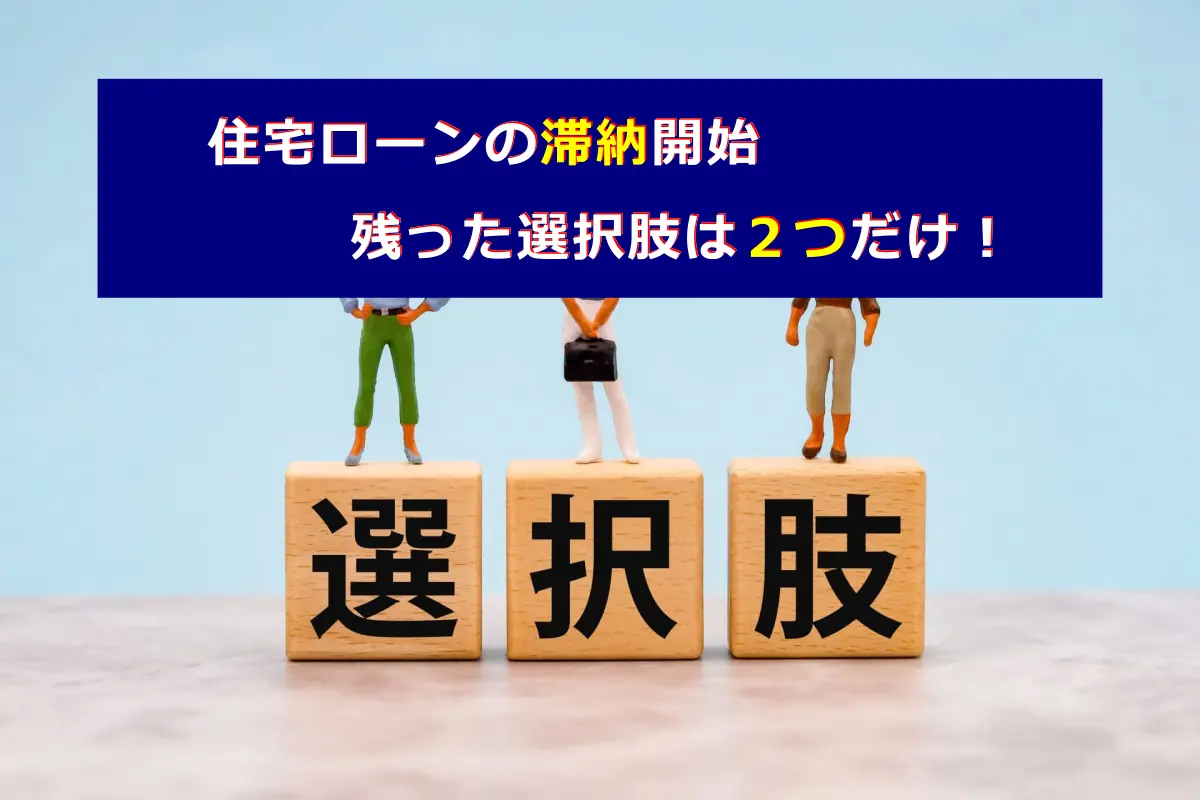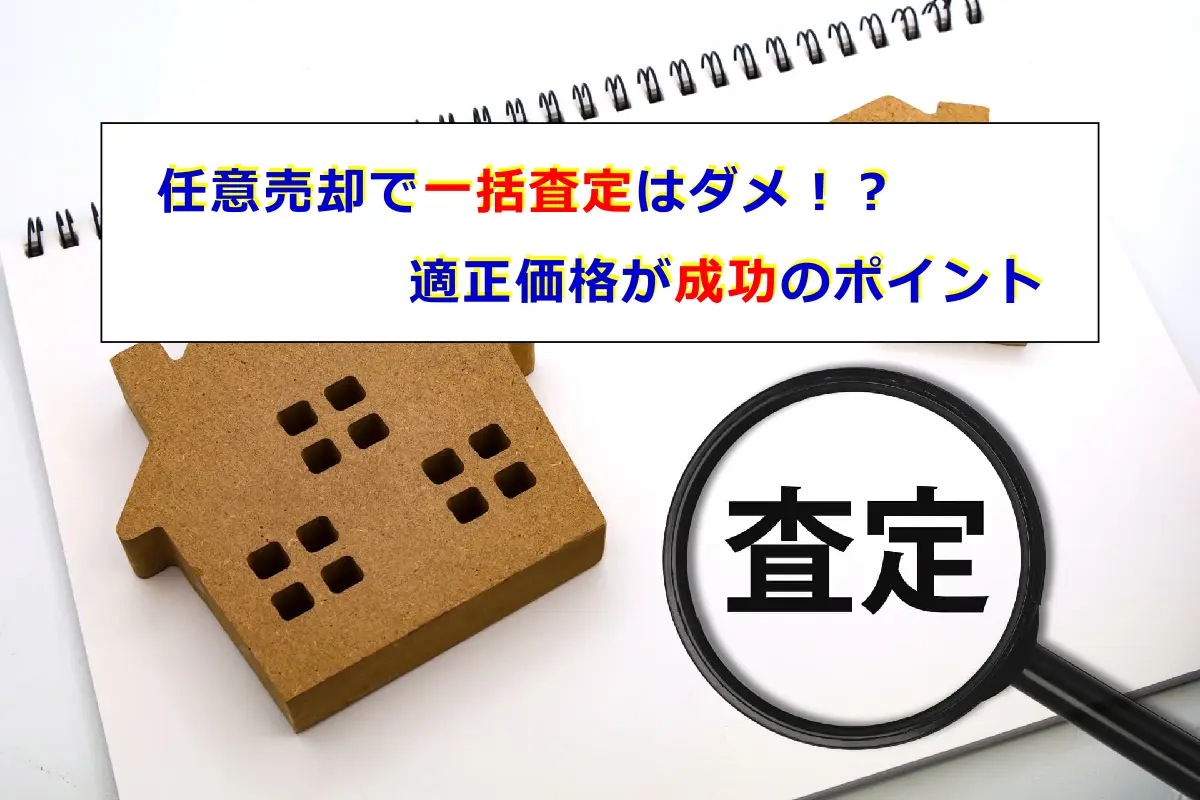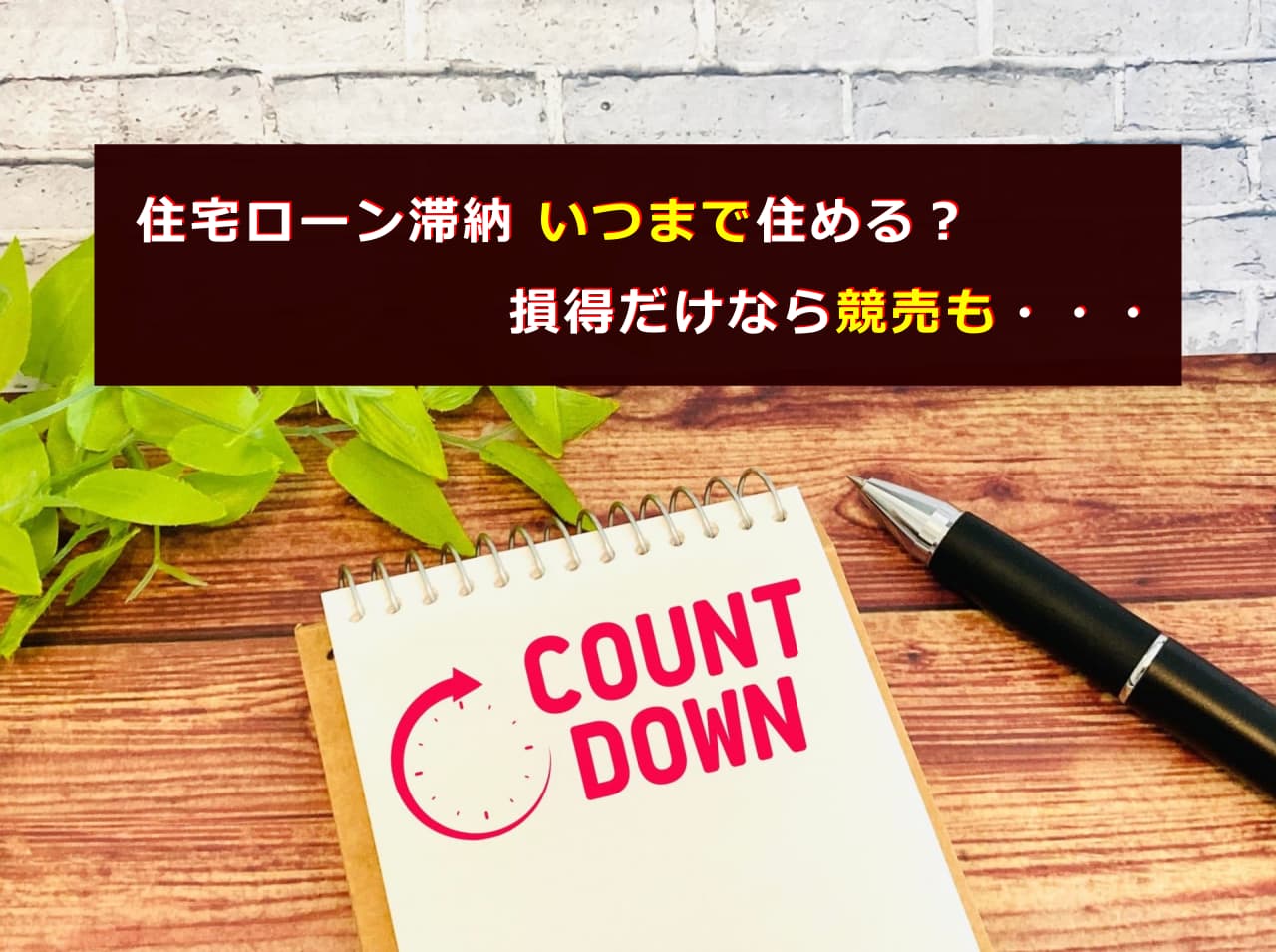土日祝日も受付中
期限の利益の喪失で住宅ローンはどうなるの?

住宅ローンを滞納したら「期限の利益喪失予告書が届いたけど」、どうすれば・・・
「期限の利益の喪失」の意味が、分からない?
住宅ローンの返済が滞ると、金融機関から「期限の利益の喪失」に関わる通知が届きます。
普段の生活では、あまり聞きなれない言葉です。
しかし、これらの通知を放置すると、住宅ローンの返済はより一層望まぬ方向へ進んでしまいます。
この記事は、「期限の利益の喪失」や「期限の利益喪失予告書」について、FP&不動産コンサルの有資格者が解説します。
住宅ローンも含め、他の不動産担保ローンでも共通する内容のため、返済でお困りの方は参考にしてください。
目次
期限の利益とは|期日までは返済しなくてもいいというメリット

「期限の利益の喪失」については、「期限の利益」と「喪失」と2つに分けると理解しやすくなります。
まず「期限の利益」とは、期日までに返済を待ってもらえる債務者(借手)側のメリットのことで、「喪失」によってそのメリットを失うことになります。
通常、住宅ローンのように高額なローンを組む場合は「毎月〇日迄に10万円返済する」などといった契約を交わします。
この契約には「毎月〇日迄は返済しなくてもいい」という意味が含まれます。
仮に金融機関が「◯日までに全額返済してください!」と迫っても(ありませんが・・・)、期限の利益によって、金融機関の返済依頼を断ることができるのです。
「期限の利益を喪失」とは、期限の利益というメリットを失うことを意味します。
続いて、その本質的な意味を解説していきます。
期限の利益=分割返済が可能
住宅ローンは、「毎月期日までに返済する」という約束の上で、分割返済を認めるものです。
金融機関は、債務者に対して分割返済の猶予を与える代わりに利息を受け取ります。
両者にとってメリットがあるからこそ、分割返済が成立するのです。
債務者が期日を守らなければ、約束は反古となり、債務者は「分割返済のメリットを失う」ことになります。
これが「期限の利益の喪失」です。
期限の利益を喪失するのは、どんなとき?

住宅ローンの契約において、「期限の利益を喪失する原因」には、次のものがあります。
〈期限の利益を喪失する原因〉
- 期日までに返済しなかったとき
- 債務整理をしたとき
- 差押えを受けたとき
- 民法第137条に該当したとき
ここからは、それぞれのケースをより具体的に解説していきます。
1.期日までに返済しなかったとき
期限の利益は、期日までに返済するという約束のもとで成り立っています。
返済が滞れば、分割返済のメリットは失うことになります。
期日までに返済するのは大前提ですが、数日の遅れで期限の利益を喪失するケースは、ほぼありません。
返済が確認できなければ、債権者は文書や電話で督促を行います。
その時点ですぐに返済すれば、期限の利益は喪失せずに済むことがほとんどです。
金融機関により異なりますが、実際のところ期限の利益喪失までの期間は、滞納開始3〜6ヶ月が目安と覚えておいてください。
遅れ遅れの返済でも、滞納が重なっていなければ大目に見てくれるケースもあります。
返済が完全にストップしなければ何とかなる!
あなたの借入先が街金(まちきん)だったら要注意
住宅ローンに限らず、不動産を担保に融資する金融機関はたくさんあります。
その中で、銀行や信金、住宅金融支援機構など社会的認知度のある金融機関(ノンバンクも含む)からの借入れていれる方は読み飛ばしてください。
しかし、そういった金融機関とは一線を画す、いわゆる街金(まちきん)だった場合は注意が必要です。
理由として、「1度でも遅れた場合は期限の利益を喪失する」など貸付条件が大変厳しいケースがあるからです。
該当者は少ないと思われますが、詳しくは「代物弁済で不動産が取られた後に任意売却で解決!」の記事を見てください。
借金のカタに不動産が取られる?
あわせて読みたい

代物弁済で不動産が取られた後に任意売却で解決!
令和の前になりますが、大阪にお住まいの方から『借金が払えなくなり、もうすぐ一戸建の自宅を取られる!その前に任意売却したい』という緊急相談がありました。 この...
2.債務整理をしたとき
期限の利益を喪失してしまう条件の1つとして、債務整理(任意整理や個人再生など)が該当します。
債務整理をする時点で、住宅ローン以外の債務を含めると返済が困難な状況にあり、約束通りの返済が期待できません。
多重債務の可能性があり、期限の利益を喪失させる原因としては、十分と認識できることでしょう。
ただし、住宅ローン以外の債務を整理する場合もあり、一概に期限の利益を喪失させるとまでは言い切れません。
債務整理はケースバイケース
3.差押えを受けたとき
この解説で差押えの対象としているのは、住宅ローンの担保となっている不動産を指しています。
住宅ローン以外に返済できない借金や支払い義務があり、差押えを受けたとなれば、債権者にはお金を回収できないリスクが発生します。
ただし、住宅ローンの場合は、担保設定時の優先順位も1番(1番抵当)が条件となります。
仮に税金の滞納で役所関係の差押えが発生しても、住宅ローンの返済が継続されている限り、金融機関が期限の利益を喪失させるケースは少ないのが実情です。
金融機関が期限の利益を喪失させないからといって、安心するのは言語道断。
差押えを受ければ、金融機関はいつでも期限の利益を喪失させることは可能となります。
滞納が無ければギリギリセーフの可能性も
4.民法第137条に該当したとき
期限の利益を喪失するケースとして、民法でも定められており、その内容は次の通りです。
次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
引用元:民法第137条
① 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
② 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
③ 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。
このうち、住宅ローンの滞納で該当するのが①②の場合です。
①については債務者が破産すると、債権者は直ちに期限の利益喪失させ、一括返済を求めます。
②は担保となる不動産を「滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。」とは、返済途中なのに勝手に建物を解体してしまうケース。
また、無いとは思いますが、故意に建物を破壊してしまうケースなどが該当します。
①②共に、詳しく解説するまでも無く、当然のケースと言えるしょう。
期限の利益を喪失すると、何が起こる?

住宅ローンの借手は期限の利益によって、分割による返済が可能となります。
それゆえに、期限の利益を喪失してしまうと、どうなるのでしょうか?
その答えは明白で、分割による返済が不可となり一括返済のみが残された方法です。
期限の利益の喪失は、債務者(借手)にとって、非常に厳しい状況であるのは間違いありません。
期限の利益の喪失 = 一括返済
期限の利益の喪失で保証会社がある場合
銀行や信用金庫など民間金融機関の住宅ローン場合、保証会社を利用するケースがほとんどです。
保証会社を利用した住宅ローンで期限の利益を喪失すると、やがて「代位弁済通知」が届きます。
代位弁済とは
何らかの理由により返済ができなくなったとき、第三者(住宅ローンの場合は保証会社)が本人に代わって借金を返済するこ。
代位弁済通知書は代位弁済が済んだことの通知となります。
あわせて読みたい

代位弁済されたら住宅ローンは保証会社から請求される
民間金融機関で住宅ローンを借りるとき、原則として連帯保証人は不要ですが、保証会社との契約が必要となります。 民間金融機関とは、皆さんが街中でよく目にする「銀...
本人の代わりに返済すると聞けば、誰かが借金を肩代わりしてくれたように感じます。
残念ながら、そう都合のいい話しではありません。
返済先がもとの借入先から保証会社に移るだけで、「代位弁済後は保証会社へ」債務者の返済義務は続きます。
それだけでなく、代位弁済されると(ほぼ)分割返済は認められず、残債は一括で返済しなければなりません。
保証会社があると、期限の利益の喪失後、金融機関が保証会社へ代位弁済の請求を行います。
そのため「期限の利益の喪失 → 代位弁済通知」の順番となります。
滞納を続けてしまう経済状況の中では、一括返済はほぼ不可能と考えられます。
かといって、何もせずに放置すれば、いずれ自宅は競売にかけられるでしょう。
フラット35を扱う住宅金融支援機構は保証会社の利用がなく、低金利のネット銀行なども保証会社を利用しないケースが多いです。
期限の利益は放棄できる
期日前にお金を用意でき、返済を前倒ししたいと望めば、期限の利益を放棄して繰り上げ返済をすることも可能です。
ただし、繰り上げ返済をしても、利息は減らない可能性があります。
これは、期限の利益の放棄について民法で以下のように定められているためです。
期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。
引用元:民法第136条2項
ここでいう「相手方の利益」とは、お金を貸した側が得られる利息のことです。
つまり、期限の利益を放棄(=繰り上げ返済)しても、債権者は利息が受け取れるという意味があります。
もっとも、債権者との契約で異なる合意があればこの限りではありません。
期限の利益を放棄した場合の利息の取り扱いについては、契約書を確認してみるといいでしょう。
金利の関係で今の住宅ローンから、他社の住宅ローンへ借換える際も繰り上げての一括返済に該当します。
繰り上げ返済に対しては、手数料を請求する金融機関もありますので、経済的な余裕ができて一括返済する場合や一部繰り上げ返済する場合には、事前に金融機関は確認してください。
期限の利益喪失予告書が届いたときの対処法は?

期限の利益喪失予告書が届いたら、これ以上事態を悪化させないため、可能な限り早く行動に移しましょう。
具体的には、以下の3点となります。
〈3つの対処法〉
- 期日までに返済する
- 金融機関に相談する
- 任意売却を検討する
〈3つの対処法〉について順番に解説します。
期限の利益喪失予告書は必ず届くの?
「期限の利益の喪失」した旨の通知や「期限の利益の喪失予告」、その他「催告書」などの書面が届くので、必ず捨てずに目を通していれば気付きます。
詳しい説明は以下の記事を参考にしてください。
あわせて読みたい

催告書の内容は必ず確認して意味を理解する
住宅ローンが払えなくなると、金融機関から様々な書類が段階的に届きます。 当然、中身は返済を促すものなので、しっかりと確認せず、そのままにしている方もいます。...
1.期日までに返済する
期限の利益喪失予告書には、返済を待ってくれる期日も記載されております。
その期日までに滞納分を返済できれば、期限の利益を失わずに済みます。
お金があることが大前提の対処法ではありますが、期限の利益を喪失した後は残債を一括で返済しなければなりません。
お金を工面できる見込みが少しでもあるなら、まずは期日までの返済に向けて行動しましょう。
2.金融機関に相談する
期日までの返済が困難な場合、借入先に相談してみるのも1つの方法です。
債権者としても、お金を回収できない事態は何としても避けたいと考えます。
少し待って返済できるなら、期日を延ばしてもらえるよう交渉の余地があるかもしれません。
何の連絡もせずに滞納するよりは、正直に事情を話した方が相手の受ける印象も大きく変わってきます。
債権者への相談だけでなく、国が定める制度も活用するのも方法の1つです。
近年は、新型コロナウイルス感染症の影響でローン返済が困難になった方向けの特則も設けられています。
〈救済措置〉
- 債権者との話し合いの際に専門家の支援を無料で受けられる
- 住宅ローンの返済を継続する条件で弁済計画を立てる
- 返済が遅れてもブラックリストに登録されない
上記のメリットがありますので厳しい状況でも諦めずに、まずは自身が該当しないか確認しましょう。
参考:法務省|新型コロナウイルス感染症の影響により借金等の返済が困難となった方へ
参考:政府広報オンライン
ただし、今後の返済自体が不可能な場合、返済できない理由を伝えても意味はありません。
あわせて読みたい

住宅ローンの滞納は銀行に相談しても解決しない!回収不能でも困らない訳
住宅ローンが払えないときは、まず銀行に相談というインターネット上のアドバイスを見かけます。 銀行に対して払えない理由を伝える機会にはなりますが、ほぼ「問題が...
3.任意売却を検討する
上記「2.金融機関に相談する」の結果が残念ながら不調に終わってしまった。
〈金融機関との相談不調〉
- 「金融機関とうまく交渉できなかった」
- 「期限の利益の喪失を避けられなかった」
このような場合は、早急に相談先を探して任意売却を検討してください。
任意売却は、債権者の同意を得た上で不動産を売却する方法です。
通常の不動産売却と同じように進められるため、第三者に「住宅ローン滞納による売却である」と知られずに売却できます。
プライバシーが守られ、精神的負担を最小限におさえられるのが任意売却のメリットです。
また、条件次第ですが同じ家に住み続けられる可能性も残ります。
債務者本人が自らの意志で不動産を手放すものであり、誰かが勝手に任意売却を進めることはありません。
任意売却を前向きに検討する場合、まずは任意売却に精通する業者へ相談しましょう。
補足として、任意売却できる期限にはリミットがあります。
期限の利益喪失後、長くても6ヶ月以上が経過するとそれ以降は、「任意売却を進めるのが困難になる」と認識してください。
期限の利益の喪失後も滞納を続けると競売のリスク

期限の利益を喪失後も返済に応じない場合、不動産は競売にかけられてしまいます。
競売とは
債務者の不動産を強制的に売却し、その代金を債権回収に充当すること。
裁判所主導で行われ、拒否はできません。
競売がはじまると、裁判所から「競売開始決定通知書」が届きます。
その後、裁判所が選任した執行官が自宅にやってきて、物件の写真撮影や居住者への聞き取り調査などを行います。
競売によって自宅が売却されると、不動産の所有権は落札者に移転し、それ以上住み続けることはできません。
自宅を奪われてしまえば、ご自身はもちろんのことご家族の人生を狂わせる可能性もあります。
競売は、債権者が貸付金を回収するための最終手段です。
金融機関も「喜んで競売の申立てをする訳ではない」ことは付け加えておきます。
競売開始前に何度も督促をしているわけですから、その時点で何らかの対処をし、最悪の事態は回避したいものです。
あわせて読みたい

競売回避の方法をFP&不動産コンサルの有資格者が解説
住宅ローンの返済が滞ると、金融機関は回収のために裁判所へ不動産競売の申立てを行います。 競売は強制力のある措置なので、落札者が落札代金を支払えば不動産の所有...
期限の利益の喪失が迫っているなら早期に相談を!

期限の利益を喪失すると、住宅ローンの残債は一括返済を求められます。
住宅ローンを滞納している経済状況での一括返済は、ほぼ不可能に近いと言えるでしょう。
一括返済ができなければ「自宅は競売」に掛けられます。
滞納を続けると、状況はどんどん不利な方向に進みます。
事態を悪化させないためにも住宅ローン滞納で悩んでいる」「期限の利益喪失予告書が届いた!」このような場合、どうするのか?
それは、任意売却に精通する業者へ一刻も早く相談することです。
あわせて読みたい

任意売却の相談で気を付けるポイント「不安をあおる業者」はアウト!
任意売却を検討する際や依頼するにあたって、最初にすることは「相談先の業者選び」です。 任意売却の相談先は規制も無いため、インターネットで検索すると実に多くの...
期限の利益の喪失【前後】で違う驚異の遅延損害金
期限の利益を喪失によって、一括請求されることは理解できたとして、デメリットはそれだけでしょうか?
実は、期限の利益を喪失によって、更なる恐ろしい事態を引き起こします。
期限の利益喪失後の恐ろしい事態とは?
期限の利益の喪失【前後】で「遅延損害金の額が驚くほど違なる」からです。
決して大げさに不安をあおっている訳ではありません。
事実として、正しく伝えております。
特に注意して欲しいのは、自宅の売却によって住宅ローンの完済が見込める方です。
それは、住宅ローンを滞納しても完済できるからこそ、遅延損害金が問題となってくるのです。
続いて、期限の利益の喪失【前後】の遅延損害金を計算してみます。
任意売却検討中の方は特に注意!
遅延損害金は「毎月の元金返済額」又は「元金」に対して算出される
まず遅延損害金とは、返済の約束期日を守らないことによるペナルティのことで、ある金額に遅延損害金の割合(○○%)を掛け合わせ請求されます。
ある金額とは「元金」又は「毎月の元金返済額」のどちらかを指します。
また、遅延損害金の割合は「年率〇〇%」として金融機関ごとに定められています。
住宅ローンの遅延損害金は、どこの金融機関も概ね年率14%(以下、年率の記載を省略します)以上が多いでしょう。
〈遅延損害金の計算式〉
- 「毎月の元金返済額」×「〇〇%」=「遅延損害金」
- 「元金」×「〇〇%」=「遅延損害金」
※ 〇〇%は遅延損害金の年率割合
※ 計算式は年間の遅延損害金が算出され、365で割れば1日あたりの金額となります。
遅延損害金の計算は「毎月の元金返済額」又は「元金」のどちらちらかに、遅延損害金の割合を掛けて計算します。
それでは、遅延損害金の計算は「毎月の元金返済額」又は「元金」のどちらを基準にするのでしょうか?
続いて、判断基準を解説します。
期限の利益の喪失【前後】で「毎月の元金返済額」か「元金」か決まる
ご自身の遅延損害金を「毎月の元金返済額」で計算するのか?
又は「元金」で計算するのか?
その違いは、期限の利益の喪失【前後】がポイントになります。
まだ「期限の利益を喪失前」の方は「毎月の元金返済額」で計算
もう「期限の利益を喪失後」の方は「元金」で計算
住宅ローンを滞納中でも、期限の利益の喪失前か後かの違いと覚えておけば大丈夫です。
〈期限の利益の喪失前後の違い〉
- 「期限の利益の喪失前」は、まだ分割返済は可能
- 「期限の利益の喪失後」は、もう分割返済は不可
「分割返済ができるのか?・分割返済ができないのか?」の違いです。
それでは、上に載せました〈遅延損害金の計算式〉に当てはめてみます。
〈遅延損害金の計算式〉
・期限の利益の喪失前
「毎月の元金返済額」×「〇〇%」=「遅延損害金」
・期限の利益の喪失後
「元金」×「〇〇%」=「遅延損害金」
遅延損害金の計算が「毎月の元金返済額」か「元金」のどちらを基準にするのか分かったと思います。
次は、「期限の利益の喪失前」と「期限の利益の喪失後」で、実際に計算してみましょう。
期限の利益の【喪失前】の遅延損害金の計算
住宅ローンの滞納中でも、期限の利益の喪失前の遅延損害金の計算は、以下の式になります。
〈期限の利益の喪失前の遅延損害金の計算式〉
「毎月の元金返済額」×「〇〇%」=「遅延損害金」
※ 1年分の遅延損害金が算出されます。
ここで「毎月の元金返済額」について少し補足しておきます。
毎月の元金返済額とは
利用者の大多数を占める元利均等払いのケースで簡単に説明します。
元利均等払いは金利の変動が無ければ、毎月同じ返済額となります。
また、返済額は同じですが、内訳は元金返済額と利息に分けられます。
(例):7万円の返済額に対して内訳は元金返済額4万円の場合、利息3万円となります。
内訳は返済が進むにつれて元金返済額の割合が増え、利息の割合が減ります。
毎月の返済額が7万円(元金返済分4万円+利息分3万円)として実際に計算してみましょう。
本記事内では、住宅金融支援機構の遅延損害金を用いて年率14.5%とします。
〈期限の利益の喪失前の遅延損害金の計算例〉
・4万円×14.5% =5,800円
※ 年率のため1年間の遅延損害金が5,800円として算出します。
・1日の遅延損害金は?
5,800円÷365日=約16円(四捨五入)
・2週間の遅延損害金は?
16円×14日=224円
・1か月の遅延損害金は?
16円×30日=480円
※ 元金返済分4万円に対して遅延損害金が課せられます。
1日あたり約16円
2週間(14日)で僅か224円
1カ月で480円と500円にも満たない額となります。
正直なところ、それほど負担の大きい金額ではありません。
期限の利益の喪失前は遅延損害金の負担は少ない
期限の利益の喪失前の遅延損害金は滞納3回~6回まで
期限の利益の喪失は金融機関によっても異なりますが、概ね3回か6回と覚えておいて差し支えありません。
3回としていますが、3か月分の返済額が滞った状況です。
6回の場合は、6か月分の返済額が滞った状況となります。
先ほど、〈期限の利益の喪失前の遅延損害金の計算〉として1年間の遅延損害金が5,800円と書いていますが、遅延損害金の割合が年率○○%としているためです。
現実としては、多くても6回滞納したら期限の利益を喪失してしまうので、あくまでも計算上であることをご理解ください。
従いまして、期限の利益の喪失前の遅延損害金が請求される期間は短く、その額も少ないため特に気に掛ける必要性はあまり感じられません。
ただし、全くの0円ではありませんので、経済的に厳しい状況を考慮するなら、無駄な支出を少しでも抑えられるよう努力することは大切です。
多くても滞納6回で期限の利益は喪失
期限の利益の【喪失後】の遅延損害金の計算
期限の利益の喪失後の遅延損害金の計算は、以下の式になります。
〈期限の利益の喪失後の遅延損害金の計算式〉
「元金」×「〇〇%」=「遅延損害金」
※ 1年分の遅延損害金が算出されます。
住宅ローンを例にとり元金を2,000万円として計算します。
遅延損害金は住宅金融支援機構の年率14.5%とします。
〈期限の利益の喪失後の遅延損害金の計算例〉
・2,000万円×14.5%=290万円
※ 年率のため1年間の遅延損害金が290万円となります。
・1日の遅延損害金は?
290万円÷365日=約7,945円
・2週間の遅延損害金は?
7,945円×14日=111,230円
・1か月の遅延損害金は?
7,945円×30日=238,350円
ひとたび、期限の利益を喪失してしまうと遅延損害金の額は跳ね上がります。
元金2,000万円に対して1年で、なんと290万円の遅延損害金が発生します。
1日あたり約8,000円
2週間で11万円オーバー
そして、1か月でなんと約24万円ほどになります。
毎月24万円を返済しても、元金は1円も減らない計算です。
いかに恐ろしいペルナルティなのか、ご理解頂けることでしょう。
期限の利益の喪失後の遅延損害金はもはや懲罰的な制裁金
保証会社が遅延損害金を請求するときも同じ
保証会社が請求するとき、遅延損害金はいつから発生するのか?
元金全額に対して遅延損害金が請求されるのは、期限の利益の喪失後と上にも書いてきました。
保証会社を利用している場合、遅延損害金はどうなるの?
保証会社を利用していると期限の利益の喪失後は銀行など金融機関の手を離れて、管理が保証会社へ移ります。
これを代位弁済といい、保証会社が銀行などへ肩代わりして返済することは、すでに解説しました。
保証会社の利用がある場合、「代位弁済した日から遅延損害金が発生」します。
〈保証会社の遅延損害金の計算式〉
「代位弁済額」×「〇〇%」=「遅延損害金」
※ 1年分の遅延損害金が算出されます。
元金から代位弁済額に代わっただけでと見れば、分かりやすいでしょう。
保証会社についても遅延損害金は住宅ローンの場合、概ね14%以上と覚えておいてください。
住宅金融支援機構やプロパー融資等の保証会社の利用が無い場合、代位弁済されません。
保証会社は代位弁済後に遅延損害金の請求
※ プロパー融資とは銀行や信金等が保証会社や保証協会を利用せずに直接貸し付けている融資のこと。
期限の利益の喪失後は遅延損害金も莫大
住宅ローンが払えなくなると分かった時点で、売却によりローンが完済できそうな方は本当に注意してください。
期限の利益の喪失前に売却を済ませなければ、手元に残せる現金が遅延損害金によって、あっという間に減ってしまいます。
任意売却により残債が発生してしまう方とは異なり、金融機関は回収可能な場合は、一切妥協せずキッチリ回収します。
つまり、不動産の売却代金が元金にも満たないケースでは、金融機関も遅延損害金どころの話ではありません。
その反面、回収が望める方からは遅延損害金も含めトコトン回収し、それでも「残ればやっと残額を受取れる」と理解して下さい。
従いまして、任意売却でも住宅ローン完済の目途が立つならば、期限の利益の喪失前に売却を済ませることは金銭面でも非常に有効です。
この仕組みを知っているだけで、より多くの現金を手元に残せる可能性があります。
現金が多ければ、再スタートも楽になり、その後の選択肢も広がります。
滞納の積み重ねにより、期限の利益の喪失後に元金又は代位弁済額に対し、年14%を超える遅延損害金が請求されることは、非常に大きなハンデキャップとなります。
多額の遅延損害金で貴重な現金を失うより、早めに行動するほうがメリットは大きいのではないでしょうか。
完済の目途があれば早期の売却が金銭面でもメリット大!
あわせて読みたい

遅延損害金とは|利率や計算方法、免除の方法などを解説【住宅ローン】
住宅ローンを滞納すると、気になるのが遅延損害金の存在です。 遅延損害金とは、約束の期日までに住宅ローンの返済が行われなかった時に発生するペナルティのことです。...
相談者が期限の利益の喪失前に売却を決めた訳
ここからは、当事務所で「期限の利益の喪失前に任意売却」を済ませた相談者の実例を紹介します。
新築マンションを35年払い100%住宅ローンの借入れで購入したものの、返済ができなくなり任意売却を決めたAさんのケースです。
〈依頼者のAさん〉
- 横浜市在住 40代 自営業
- 債権者 住宅金融支援機構(1番抵当) 銀行(2番抵当)
- 住宅ローンの滞納状況 1回
- 管理費・修繕積立金の滞納状況 2回
- 残債 2社合計 約1,700万円
- その他 横浜市の差押え
早期売却で期限の利益の喪失を回避
Aさんは相談のタイミングが早く、1回目の滞納後、すぐに当事務所へ相談となりました。
「期限の利益の喪失前」のため、早期に売却できれば、元金に対しての遅延損害金も発生せず、損失を極めて減らせます。
また、売却価格も残債を軽く上回ることが予想されました。
速やかに売買契約まで進めばオーバーローンではないため、買主様より手付金を直接Aさん自身が受取ることができます。
その手付金から、住宅ローンと管理費等の滞納分を解消することも可能です。
ご自分の置かれた状況と遅延損害金の事実を知り、Aさんは即時に任意売却の決断をされました。
依頼者の状況を踏まえた段取りが重要
余談となりますが、オーバーローンについて少し触れておきます。
任意売却は、売買価格より住宅ローンの残債が上回る(オーバーローン)のケースが多く、売買契約時に手付金を受取っても、実際は任意売却に携わる仲介業者が取引終了時まで全額を預かります。
そのため、任意売却の売主は受取った手付金を取引終了時までは、使うことはできません。
なぜ、このような仕組みなのか?
任意売却は損失を被る金融機関が、売買契約後にNGを出す場合もあります。
そうなると、任意売却はいったんストップし売買契約は、白紙解約となります。
手付金を渡して使ってしまうと契約が白紙解約となった場合、経済的に苦しい売主が手付金を返還できない可能性があるためです。
このような仕組みで取引するため、買手も安心して任意売却物件を購入できることになります。
手付金を使えた理由は売買価格が残債を上回ったから!
あわせて読みたい

住宅ローンが払えない!対処法と注意点を解説
「住宅ローンが払えなくなるかも…」そんな不安を抱えていませんか? このページでは、住宅ローンが払えなくなった場合の対処法を「マンガ」と詳細な「文章(文字)」に...
希望に沿った売却スケジュールの立案
Aさんには、引越し日の希望がありました。
そこを逆算していくと、販売開始から遅くとも2か月以内には買手を見付けなければ、間に合いません。
そのため、内見に来たお客様にも、水面下での値引き価格を提示する等の販売活動も同時に行いました。
その結果、販売開始から、「2か月目に入ってすぐに2,400万円での売買契約が成立」、引越しも希望通りの日程で取引を進めることができました。
経済的に厳しい状況でも、子供の転校などタイミングも考慮してあげなければ家族も気の毒です。
できる限り希望に沿うのが、依頼された業者としては当然です。
スケジュール通りの売却は難易度が高い
実は、不動産をスケジュールに合わせて売却を進めるのは、簡単なことではありません。
その理由として、仮に買手が見付かったとしても、多くの方が金融機関からの借入を条件に購入します。
買手側は金融機関から審査をパスしなければ、購入することができません。
実際には段階を踏まなければ、「本当に購入可能な買手かは分からない」のです。
買手も1つの金融機関だけでは不安なため2~3社の金融機関に申込んだりと、あっという間に1~2か月が経過してしまいます。
買手の段取りが悪くて、期限の利益を喪失してしまっては元も子もありません。
金融機関の審査は意外に手間取るので要注意
横浜市の差押えはどうなったのか?
気になる方も多いと思いますので、横浜市(以下、役所)の差押えについても書いておきます。
Aさんは自営業者だったため社会保険ではなく、国民健康保険に加入しておりました。
国民健康保険の加入者ならご存じかと思いますが、家族の人数分だけ国民健康保険料は加算されます。
4人家族のAさんも、かなりの負担となり国民健康保険料の滞納が続いてしまいました。
その結果、約4年ほど前から役所に自宅マンションを差押えられていいたのです。
更に約2年ほど前には、固定資産税の納付もできず、同じ役所でありながら2件目の差押えも受けてしまいました。
ただし、遅れながらも納付していたために、約50万円ほどが差押えの解除に必要な金額でした。
念のため付け加えますが、役所も延滞金も含めてキッチリ請求してきます。
最終的には役所の差押えがあっても、全額を納付できる目途があれば、差押えの解除は可能となります。
従いまして、Aさんのケースでは、準備だけしていれば全く問題なく取引できます。
ここで少し思い出してください。
期限の利益を喪失する原因として「3.差押えを受けたとき」がありました。
そこにも書いた通り、差押えは期限の利益の喪失理由になるものの、実際は見過ごされる正に実例となります。
役所の差押えは納付できれば問題無し!
差押えの不思議
役所からの差押えって聞くと、「もう不動産に住むこともできない・・・」と思われがちですが、実はそんなことはありません。
あわせて読みたい

不動産が差押え、どうなるの?原因、影響、解除方法を徹底解説
不動産の差押えとは、一体どういうことなのか? 自宅が差押えられたら、大変なことになるのでは・・・ 不安になるのは、間違いありません。 実際に「不動産を差押えら...
あわせて読みたい

役所の差押えが障害に!税金や健康保険料の未納で競売も
景気の回復を実感している人が、実際は少ないような報道を見かけます。 その反面で財務省の発表によると令和4年度の一般会計の税収が過去最高となりました。 税収に関...
住宅ローンを完済し残った金額
早期の売却が必要なため、表向きの販売価格から値下げも行いましたが、売却の諸経費を引いても残った金額を計算すると、なんと550万円となります。
〈Aさんの手元資金〉
- 売却価格 2,400万円
- 住宅ローン残債 1,700万円
- 横浜市差押え分 50万
- 諸費用 100万円
2,400万円ー1,700万円ー50万ー100万円=550万円
もちろん、この中から引っ越し費用や転居後の準備資金に充てたため、手元に残せる金額は減ってしまいますが、再スタートするには十分な金額です。
住宅ローンも完済し、不安も無くなりAさんにも満足して頂けました。
手元資金に余裕があると再スタートも心強い
期限の利益の喪失前の売却が賢明な理由
多くの任意売却の場面では、売却額を住宅ローンの残高が上回り、遅延損害金どころか元金にも届かないため、あえて期限の利益の喪失をするまで待つこともあります。
そうなると遅延損害金は、あまり問題とはなりません。
しかし、売却すれば完済が見込めるケースでは、債権者は遅延損害金もしっかりと請求し回収します。
従いまして、この様なケースでは、遅延損害金は大変大きな負担となります。
ここで、仮にAさんが「期限の利益の喪失した場合の1か月の遅延損害金」を計算してみます。
〈遅延損害金の計算〉
- 住宅ローンの残元金 1,700万円
- 遅延損害金 14.5%(年率)
- 1,700万円 × 14.5% ÷ 365日 = 0.675万円(1日につき6,750円)
- 0.675万円 × 30日 = 20.25万円(1か月)
なんと、恐ろしいことに期限の利益を喪失していたら、毎月約20万円の遅延損害金が発生していました。
仮に同じ価格でマンションが売却できても、1か月遅れるごとに、その分手元から約20万円減る計算です。
現金を残せたもう1つの大きな理由
Aさんは新築マンションを頭金無しの35年ローンで購入しました。
実は今回売却した新築マンションの購入時、最終的に売れ残っていた部屋を大幅な値引き交渉の末、購入しておりました、何とその額650万円とのこと。
もちろん、購入したAさん自身も「驚いた!」と思い返していたほどです。
購入した時期も良かったのと、マンション業者の売り急いでいたタイミングにピッタリと合っていたため、この様な値引きが実現したものと思います。
もともと、Aさんも『値引きが無ければ購入していなかった』と言っていました。
結果的には、この大幅な値引きが無ければAさんの手元には一銭も残らず、むしろマイナスだった計算になります。
Aさんの購入動機は大幅な値引きがあったから!
早めの相談は誰にでも可能
Aさんのように、購入時の大幅な値引き、売却時に数百万円を手元に残せるのは、極めてまれでしょう。
しかし、早期に行動することは、「誰にでも例外なくできる」ことです。
多くの方は、任意売却で残債の問題が生じます。
更にその前には、競売という最悪の事態に遭遇する可能性があります。
競売を回避するには、まず早めに相談し対処することが最優先課題となります。
Aさんは運が良いと感じる方も多いと思いますが、決してそうではありません。
このように多額の現金を手元に残せたのは、競売はおろか期限の利益の喪失前に相談し、マイホームを手放す決断ができたからです。
この決断は、本当に賢明な判断のもとに出した答えです。
命運を分けたのは、「早期に相談できた」から、期限の利益を喪失の詳細を知り行動したことは大きな結果となって表れました。
マイホーム売却の決断は迷いが生じる
あわせて読みたい

競売回避の方法をFP&不動産コンサルの有資格者が解説
住宅ローンの返済が滞ると、金融機関は回収のために裁判所へ不動産競売の申立てを行います。 競売は強制力のある措置なので、落札者が落札代金を支払えば不動産の所有...